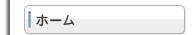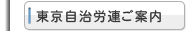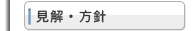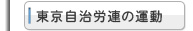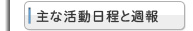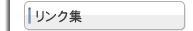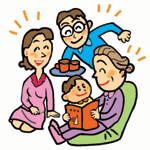自治労連都庁職2009年度運動方針
2008年10月22日
都庁職大会議室
自治労連都庁職第8回定期大会決定
2007年の参議院選挙で自民党・公明党の大敗で、国民の要求が前進する方向で政治が動きつつあります。労働者に低賃金と不安定な雇用を押し付け、「ワーキングプア」拡大の原因と批判されてきた労働者派遣制度見直しの報告書が、厚労省派遣法研究会から発表されたり、再度派兵が強行されましたがインド洋から海上自衛隊の撤退、薬害C型肝炎被害者救済法案の成立、原爆症認定集団訴訟の新基準の決定・実施、後期高齢者医療制度が参議院で廃止法案可決など、また、憲法の問題では、イラクでの自衛隊の「対応措置」の事実を違憲とする名古屋高裁の判決を引き出しています。
アメリカの強い要望による、新テロ特措法が来年1月に期限切れになることから、臨時国会に延長案を提出し、成立させる構えや「経済財政改革の基本方針」(骨太方針08)では、社会保障の自然増を毎年2200億円も削減する方針を継承することをもりこんでいます。
しかし、「構造改革」の名で大企業の儲けを応援し、国民の生活を痛めつけるだけの政治が貧困と格差を耐え難いまでに拡大し、日本経済そのものを破綻させてしまいました。外交についても、アメリカ言いなりで憲法を踏みにじり自衛隊を海外に派兵する政治に固執したことが国民との矛盾を広げただけでなく、アフガニスタンなどの事態を平和的に解決するうえでの障害を広げました。
福田首相は、8月の内閣改造で支持率上昇を画策しましたが、国民の強い批判の前にわずか1年足らずで首相を辞任しました。マスコミ各誌は、「きわめて異常、無責任としか言いようがない」(朝日)「政権を放り出すのは異常事態であり、国益を損ねる行為でもある」(毎日)など自民党に政権担当能力がないことを指摘しています。
東京都では、石原都政のもとでオリンピック招致への莫大なインフラ整備予算の問題、豊洲新市場予定地の土壌汚染問題、破綻している新銀行東京への400億円追加出資の問題などで都政モニターアンケートでは、「都政に対する満足感」では、満足は42%、都政への不満は58%と石原知事が就任した1999年以降始めて「不満」が過半数を超えました。
来年の都議会選挙に向けて、都民の福祉・医療・教育などを重視する都民生活向上のため、都政の転換が求められます。
自治労連都庁職は、自治労連がすすめる組合員に対しては、(1)情勢の変化を職場に伝え、きめ細かく職場懇談会を進める(2)「私の憲法・みんなの憲法」学習運動などを通じて、自治体と自治体労働者のあり方を語り確信する(3)「だれもが参加しやすい」組合活動のスタイルを工夫することなど追求します。
また、自治体労働者運動の原点である(1)地域・自治体の主人公は住民であることを貫く(2)地方自治体の役割は住民福祉の増進であることを確信し、住民とともに充実の方向を提起する(3)全体の奉仕者としてすべての住民と地域を視野において共同を追及し、自治体労働者としての社会的役割の発揮をしていきます。
<この1年間を振り返って>
第3期石原都政の下、東京都の財政は過去最高の都税収入を背景にして、一般会計だけでも7兆円近くに膨らんでいます。本来なら、昨年の都知事選挙で公約した個人都民税の減免措置などを始めとした、都民生活向上のために潤沢な財政を使うべきですが、石原都政はそんなつもりはさらさらなく、三つの無駄遣いを強行しています。
それは、①築地市場の豊洲移転5000億円 ②破綻した新銀行東京への400億円の出資と500億円の補正予算 ③2016年オリンピック?に10兆円です。
その一方で、石原都政は2009年度予算編成に向けた依命通達の中で、「都財政をめぐる環境は、明らかに悪化の方向に転じている」と述べ、都民施策の充実に目を向けることを拒否しています。
東京都病院経営本部は、2001年12月「都立病院改革マスタープラン」を発表し、それに基づいた「都立病院改革実行プログラム」で16ヶ所ある都立病院を8ヶ所にする計画を発表しました。1ヶ所は廃止、3ヶ所を公社化で現在12ヶ所になっています。今後、1ヶ所を独立行政法人化にし、1ヶ所を公社化、3小児病院を統廃合する予定です。また、統合した小児総合医療センターを含め、4ヶ所をPFIで運営することが決まっています。都立とは名ばかりの病院を建設しようとしています。
都立病院の生命線である民間では採算が合わなくて経営ができない、救命救急・周産期・小児・感染症・精神など不採算・行政医療を担っている都立病院への一般会計からの繰り出し金100億円も削減(99年度496億円から07年度391億円)したことは、地方自治法の「地域住民の生命と健康を守る」ことを目的とした自治体の任務を放棄したものです。
特に、都議会第三回定例会では、老人医療センターを独法化するための定款(組合で言えば規約のようなもの)と都島病院を都立病院から外してしまうという条例改正が提案されました。
しかし、こうした石原都政の攻撃に対して、私たち自治体労働組合と都民との共同による粘り強い闘いが展開され、石原都政の描いている「都立病院改革」は当初の予定通り進んではいません。
自治労連都庁職は都立病院問題に重点を置き、衛生局・養育院両支部の要請に基づき、東京自治労連の中に専管の対策委員会を設置していただき、昨年のミニパンフに引き続き、本年度はパンフレット「都立病院は直営のままで」を発行し、普及に努めてきました。
又、職員の労働条件にかかわる課題として、教育庁支部の坂本通子さんが超過勤務手当の不払いに対して東京地方裁判所に訴えたことを受けて、この問題についても自治労連・東京自治労連として取り組むことを要請し、現在、その勝利とともに都庁から不払い残業の一掃と慢性的超過勤務の縮減を求めて取り組みを進めています。
その他、各支部においてそれぞれが抱える課題を中心にして、都民生活優先の都政を目指して運動を進めています。
しかし、こうした運動を支えるための自治労連都庁職組織の強化拡大に関しては、各支部の奮闘にもかかわらず、石原都政の引き続く「自治体構造改革」における職員定数削減などにより組合員数が激減し、組織の維持にも支障をきたしています。
こうした下で、東京自治労連は組織財政の検討委員会を設置し、その答申に基づき、大胆な見直しを今次大会で決定することとしています。この提起は、財政上的に非常に大きな負担をしている自治労連都職労内の組織として、自治労連都庁職にとっても極めて大きな影響を受けざるを得ません。
私ども自治労連都庁職としても、不退転の決意を持って組織と財政の見直しを行って、この難局を克服していく必要があります。
Ⅱ 私たちを取りまく情勢
1 国民・労働者切捨ての福田政権
参議院選挙以来「新自由主義」の矛盾が一気に噴出し、労働者・国民の要求が前進しつつあります。小泉・安倍内閣が推し進めてきた「構造改革」は国民生活のあらゆる分野で矛盾を露呈しています。福田=自・公内閣も「構造改革」路線を踏襲し、原油高騰など緊急対策でも国民に背を向けています。後期高齢者医療制度の廃止や社会保障制度の充実、労働者派遣法の抜本改正、中小企業支援強化と地方経済の立て直し、大企業・大資産家優遇税制を正し、暮らしを支える財源づくりなどです。
年収が200万円に満たない労働者が1千万人を超え、貧困打開と国民生活擁護が焦眉の課題となっています。無権利状態に等しい派遣労働者の規制緩和から規制強化へと派遣労働者保護法の制定が一刻も早く望まれます。
また、社会保障費の自然増を毎年2,200億円削減する政策をすえ、年金、医療、介護、障害者、生活保護など社会保障の全ての分野で負担増・給付減を強行してきました。この政策の矛盾が爆発したのが、後期高齢者医療制度の強行でした。
厚生労働省は、08年版厚生労働白書を公表しました。国民に重要と考える社会保障分野の回答では、「老後の所得保障(年金)」(72%)が最多で、「老人医療や介護」(56%)、「医療保険」(37%)となっており、国民が将来の生活資金確保に不安を感じている実態が浮き彫りになりました。
また、06年度の社会保障に関する意識調査の結果を公表しました。老後最も不安を感じるのは何かの回答では、「健康」(47,4%)がトップでしたが、「生活費」が前回より6.5%増の33.3%に急増しています。その内訳について、20代45.4%、30代50.7%40代43.6%と若い世代に将来の生活不安が広がっています。
アメリカ従属政治から脱却し、平和日本への転換と憲法を守る闘いがますます重要になっています。アメリカのイラク侵略は5年を超えベトナム戦争に次ぐ2番目に長い戦争となり、戦費支出は第二次世界大戦につぐものとなりました。新テロ特措法を今年1月の臨時国会で、強行成立させ直ちに昨年11月の旧法期限切れで撤退していたインド洋での給油活動を再開しました。その新テロ特措法が2009年1月で期限切れになります。インド洋での給油活動は、アフガン戦争開始の翌年01年11月に始まりました。この6年間約587億円がつぎ込まれさらに新法下の1年間では90億円の予算が計上されています。
2004年6月に「9条の会」を立ち上げられ、「日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ改憲のくわだてを拒むため、一人ひとりができるあらゆる努力を今すぐ始めることを訴えます」とアピールを発表しました。現在7千を超える「9条の会」が様々な運動を展開しています。
このような世論に押され、今年4月17日名古屋高裁は「航空自衛隊がイラクで行っている米軍への空輸支援が憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」と断じました。判決は道理の通った画期的なものです。この判決に対して、福田首相は「裁判のためにどうこうする考えはない」と述べ、イラク派兵を継続しています。
読売新聞が毎年発表している恒例の「憲法」世論調査で、憲法「改正」に反対が賛成を上回りました。1993年以来15年ぶりです。その理由も「世界に誇る平和憲法だから」がトップ、「基本的人権、民主主義が保障されているから」も増加しています。改憲正論をリードしてきた「読売新聞」の調査だけに注目されます。
7月、都庁においても憲法を守り、9条を広げ、平和な日本と世界に貢献するために、100名におよぶ参加者によって「都庁9条の会」が立ち上がりました。改憲論者石原都知事の足元から一人ひとりが立ち上がり、行動を起こしていくことを確認しています。
2 東京都をめぐる情勢
3期目の都知事選挙を制した石原知事もトップダウン事業の破綻が浮き彫りになってきています。第一は、オリンピックのインフラ整備では外環道や築地・羽田間のトンネル道路、競技施設整備ではメインスタジアムなどの用地費や液状化対策など加えれば総額9兆円を超える巨大な浪費なることが必死です。第二は、新銀行東京の決算で1千億円を超える累積赤字が発表されるなかで、損失補てんするために400億円の追加出資を行うなど、破綻した新銀行東京に都民の"税金をドブに捨てる"ものだという都民の批判を無視して強行しました。さらに、資本金から1,016億円を減資することを決め銀行設立時に都の税金から出資した1千億円のうち、854億円を失うものであり到底許されることではありません。第三に、深刻な汚染が明らかになった豊洲への築地市場の移転計画です。豊洲地区の土壌調査では、発がん性のあるベンゼンが環境基準の4万3千倍に達した地点や、毒性の強いシアン化合物では検出限界の860倍という地点がみつかりました。このような事実が明確であることから、移転を見送って築地での建て替えが改めて主張されているにもかかわらず、都は築地市場の跡地に東京オリンピックのメディアセンターにする計画があり、移転を固執しています。
このような強引な都政運営に対して、08年度の都政モニターアンケートでは、都政に対する満足度が前年比9.4ポイント減の42%で、過半数を割り込みました。また、都政への不満が58%で、その理由として、東京都が400億円の追加出資した新銀行東京の問題をあげた人が最も多くありました。
3 自治労連都庁職の運動と取組み
自治労連が結成されてから2009年で20周年を迎えます。来年の自治労連全国大会が東京で開催されることが決定されました。引き続く「30万自治労連」をめざすその一翼を自治労連都庁職も担っていきます。
自治労連が提起している「見直そう、問い直そう、仕事と住民の安心安全」運動は自治労連都庁職のなかにも着実に前進しています。
教育関係支部では、日の丸・君が代を強要し、それに反対する教師を処分する東京都教育委員会との闘いや30人学級実現など民主教育実現、不払い残業代支払いを求めて東京地裁に提訴し闘っています。東京の農林水産業を守り発展させ食料自給率向上を目指す運動、大企業中心の都財政の予算を中小企業対策のための予算に振替させる、増え続ける危害・危険、悪質巧妙化する悪質商法から消費者を守る闘いは長い間培ってきた伝統です。
環境破壊の開発一辺倒を止め、大企業中心の臨海副都心開発見直しを求める闘いは、鈴木都政時代から継続している息の長い闘いになっています。保健・衛生・福祉関係支部の都立病院のPFI,地方独立行政法人化、公社化、保健所統廃合反対運動などは、石原知事就任以来からの闘争になっています。
都営住宅の新規建設は9年連続ゼロ、建設は1DK・2DKが中心で住宅面積はミニマムなど都民の住まい確保のための闘いなど中立・住宅支部も協力共同闘争を行っています。税務関係支部による民主的税務行政の闘いは、三位一体の地方税制改革による地域間の税収格差の是正について、地方交付税の拡充を持っておこなうのが基本であり、これまで減税しすぎた法人税の税率を戻すことや租税特別措置法の見直しによる課税ベースの拡大などを提言し、都民本位の抜本的税制改革の検討を主張しています。
国が社会保障費2200億円を毎年削減する中で、地方自治体は住民のいのちと健康、暮らしを守るためその防波堤にならなければなりません。各支部の多様なたたかいがあり、地域住民の繁栄があってこそ自治体労働者の喜びやモチベーションが上がります。
Ⅲ 闘いの基調
自治労連第30回定期大会では、基調報告の中で憲法を国と地方の隅々に生かす道であり、地方自治を拡充し、自治体・公務公共関係者がその役割を発揮し、誇りを戻し、要求を実現し、情勢の激変と自治労連への期待に応えるために①職場を基礎に組合員の要求や職場の願いにしっかりと向き合い、②要求を拒む根源に立ち向かう対政府闘争として発展させ、③それを有機的に結んで中央、地方、単組、職場が一体となったたたかいをすすめ、④そして自治体労働組合運動の原点に立ち返り、積極的に地域に出て住民との共同を広く進めていくことを決めました。そして、大会で、この1年間を通じて運動の基調となる「4つの基調」を決めました。
自治労連4つの基調は次の通りです。
| 1 | 憲法を語り、自治体関係者との共同をすすめ「九条を守れ」の世論を集め、改憲の発議をさせない運動、憲法を生かすとりくみを自治労連の組織をあげてすすめる。 |
| 2 | 物価高騰への対策、「貧困と格差」の解消・社会保障制度の充実・庶民増税阻止、「分権改革」・道州制など「構造改革」の転換をもとめ、地方自治と公共性の拡充を国と財界に迫るとともに、積極的に地域に出て共同を広げます。 |
| 3 | すべての自治体・公務公共労働者を視野に、職場活動と要求活動をすすめ、あらゆる課題を組織強化・拡大、次世代育成、単組強化に結びつけ、「第4次中期計画」を実践し「30万自治労連」をめざす。 |
| 4 | アメリカ・財界中心の政治を国民中心に転換し、国民の願いを実現するため、年内にも行われようとしている総選挙で、私たちの要求をともに実現する勢力の前進をめざす。 |
自治労連都庁職は、自治労連の4つの基調をふまえ、次の基調でこれからの1年間組織の総力をあげたたかいを進めます。
1 憲法の改悪を許さず、国民要求実現のためたたかいます。
| (1) | 「日本国憲法」の改悪を許さないたたかいを、自治体労働組合の存在意義をかけたたたかいとして職場と地域から進めます。 |
| (2) | 米軍基地の再編強化に反対し、平和と民主主義を守るためたたかいます。 |
| (3) | 賃金引上げ、労働時間短縮、民主的公務員制度確立などの労働条件改善と医療制度改悪など社会保障制度改悪反対、最低補償年金確立、消費税など庶民大増税反対など国民の要求実現めざし、すべての労働者・労働組合との共同をすすめ国政革新のためたたかいます。 |
2 都民・都庁労働者の要求実現のためたたかいます。
| (1) | 都庁労働者の生活と権利を守るため、都労連・都庁職運動の前進をはかるための取組みを強化します。 |
| (2) | 仕事を通じて住民に奉仕する自治体労働者の役割と責任を明確にし、指定管理者制度・地方独立行政法人・民間委託・民営化・市場化テストなど自治体リストラを許さず、都民との共同を広げ住民本位の自治体建設のためたたかいます。「見直そう、問い直そう、仕事と住民の安心・安全」の運動を前進させ、自治研活動を職場から旺盛に進めます。 |
| (3) | 福祉・医療・教育・くらし・営業等の都民要求実現のため都民とともに取組みます。大企業優先の大型公共事業を中心とした「都市再生」事業に予算をつぎ込み、都政リストラの一層の推進、福祉・医療・教育・くらし・営業など都民施策の切り捨てを進める石原都政と対決し、都民本位の都政に変えるため自治労都庁職の組織の総力をあげたとりくみを進めます。 |
3 自治労連都庁職の組織強化拡大のためたたかいます。
| (1) | 東京自治労連中期計画にもとづく組織拡大の達成をめざします。 |
| (2) | 各支部の交流を深め、職場・分会・支部での組織と運動の強化をはかります。 |
| (3) | すべての支部で関連労働者の組織化の課題を追求します。 |
| (4) | 労働組合の三原則「資本からの独立」「政党からの独立」「一致する要求にもとづく行動の統一」を堅持し、組合員の政党支持、政治活動の自由を守ります。「労働組合の主人公は組合員」との立場から組合民主主義を貫きます。 |
Ⅳ 闘いの課題と具体的な取組み
1 公務員制度改悪反対、「総額人件費削減」攻撃との闘い
(1)労働基本権確立、公務員制度改悪反対の闘い
政府・財界は、「内閣の公務員」「管民の人材交流」を掲げ、公務員労働者を憲法に規定する全体の奉仕者から政権党や財界に奉仕する公務員に変質させる「国家公務員制度改革基本法案」を成立させ、公務員制度改革を加速させています。
基本法では、労働基本権について、政府の専門調査会報告での「付与」から「検討」と大きく後退しています。
憲法に反する公務員制度改革に反対し、労働基本権の付与など私たちの権利保障と公務員労働者としての役割が発揮でき制度改革を目指し取組みを進めます。
| ① | 「国家公務員制度改革基本法」など公務員制度をめぐる状況や労働基本権問題についての学習会等を進めます。 |
| ② | 「国家公務員制度改革基本法」の問題点を明らかにする取り組みを進めるとともに、労働基本権の回復など民主的公務員制度確立に向けた取組みを自治労連に結集し取り組みます。 |
| ③ | 日本政府に対する3度のILO勧告を受け入れ、労働基本権回復など民主的公務員制度改革を求め、実現をせまる取組みを進めます。 |
(2)公務員の「総額人件費削減攻撃」との闘い
「骨太方針」に基づく公務員の「総額人件費削減」攻撃が一段と強められるもとで、「賃金制度は国準拠、賃金水準は地域準拠」攻撃が強化されています。
現業賃金については、総務省による現業賃金の民間類似職種との比較調査結果をもとに各自治体に対する取組み方針の策定と公表が強要され、都においても取り組み方針の策定と調査結果の公表が行われました。総務省はさらに「技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関する研究会」(4月14日)を立ち上げ、現業給与の決定について、①現在の現業給与を民間水準並みに引き下げる根拠を探り出し、②労働協約権を持つ中でもいかに引き下げの合理化を図るかという論点を研究し、現業給与の引き下げを強行しようとしています。8月11日の人事院勧告は、時短や非常勤処遇改善について勧告する一方、政府財界方針に屈し、「賃金の据え置き」と「能力・成績主義」の強化の勧告を行いました。
「骨太方針」や総務省の指導を通じた新たな賃金引下げ攻撃を跳ね返し、公務員労働者の生活と権利を守る闘いを自治労連に結集し闘うとともに、都労連・都庁職と連携し、対都に向けた取組みを進めます。
| ① | 「制度国準拠・水準地場準拠」に反対し、「生計費原則」をはじめ、「同一労働同一賃金」の原則を踏まえた賃金制度を求めていきます。 |
| ② | 「人事委員会の機能強化」による賃金抑制に対して、労使自治の破壊と人勧体制強化を許さない闘いを公務員制度改革・労働基本権回復の取組みと結合して取り組みます。 |
| ③ | 「民間賃金準拠」の攻撃に対して、地域民間賃金の底上げの取組みを地域の重要な課題と位置付け、賃金底上げ・最低賃金・均等待遇・公契約等の地域共同の闘いをすすめ、官民共同の賃金闘争を追及します。 |
| ④ | 総務省の「総人件費削減」攻撃や「査定」賃金制度、成果主義の人事制度の狙いを明らかにする学習と討論を深めます。とりわけ、総務省・都一体の現業賃金の民間準拠への引き下げ攻撃に対し、公務サービス拡充と一体となった賃金改善の闘いをすすめます。 |
| ⑤ | 管理団体に働く職員の賃金引き上げや自治体に働く非正規労働者の均等待遇、賃金・労働条件の改善を求める闘いを「最賃」改善の闘いや「雇い止め」を許さない闘いと結合し、関連労働組合と連携し進めます。 |
2 「働くルールの確立」、安心して働き続けられる職場をめざして
(1)「労働法制改悪」を許さず、「働くルール」の確立を求める取組み
「貧困と格差の是正」「ワーキングプアーなくせ」は国民的課題に広がり、企業の違法行為を告発した派遣労働者と労働組合の闘いは、派遣法改正、「日雇い派遣の原則禁止」や「専ら派遣」の規制などへと前進しています。しかし、一方で厚生労働省「派遣制度の在り方研究会」の議論では、「派遣期間制限」などの事業規制を緩和し、「多様な働き方」を肯定する方向を示しています。
「骨太2008」では、成長戦略を打ち出し、「テレワークの拡大」「勤務時間の柔軟な設定」「高齢者の成果主義賃金による処遇の多様化」など一層の安上がりと効率的雇用の拡大を狙っています。
労働法制の改悪を許さず、労働者保護法の制定、人間らしく働ける「働くルール」の確立をめざし取組みを進めます。
| ① | 最低賃金の「1000円以上」への引き上げと「全国一律最低賃金制度の確立」を求め取組みを進めるとともに、自治体での非正規・臨時職員の時給1000円以上の要求実現にむけ自治労連に結集し取組みを進めます。 |
| ② | 労働者派遣法の抜本改正と偽装請負・違法派遣を正し、労働者保護法の制定を求めます。また、自治体職場から偽装請負・違法派遣をなくす取組みを自治労連に結集し運動を強化します。 |
| ③ | 公契約条例運動を東京自治労連に結集し取り組むとともに、指定管理者制度の再指定に当たっては、学習・討論を基礎に現状と問題点を把握し、利用者・住民との共同を広げ、賃金破壊を許さない闘いと公共サービスを守る闘いをすすめます。 |
| ④ | 「雇用の金銭解決」、長時間過密労働をもたらす「労働時間規制」の除外など労働契約法、労働者派遣法の改悪など労働法制の全面的な改悪を許さない学習・行動に取り組みます。 |
(2)超過勤務縮減・サービス残業根絶、労働安全衛生活動強化をめざす取組み
「新地方行革指針」による地方公務員の人員削減は、長時間過密労働や職員の健康破壊など深刻な事態を生んでいます。職場におけるメンタル不全の急増は、自治体職場の緊急の課題となっています。「不払い・サービス残業」の根絶、安心して働ける職場環境の改善にむけ取組みをすすめます。
| ① | 36協定締結の取組みを重視し、労働安全衛生法の「過重労働の総合対策」の職場での後退を許さず、公務災害、メンタルヘルスなど職員の健康を守る労働安全衛生活動の取組みを強化します。 |
| ② | 蔓延する長時間労働の解消、不払いサービス残業をなくし、休暇制度の拡充、労働時間を短縮する取組みを進めます。とりわけ、教育庁支部の坂本通子さんの「不払い超過勤務手当支給裁判」について教育庁支部と連携し勝利に向け取り組みます。 |
| ③ | 国に遅れること無く所定勤務時間の短縮が行われるよう都労連・都庁職と連携し取組みを進めます。 |
| ④ | 職場における昇任・昇格差別の是正、セクシャル・ハラスメントの防止、ポジティブアクション(積極的な差別是正措置)の推進、苦情処理の第三者機関の設置など男女機会均等法に基づく、民主的で安心して働き続けられる職場づくりをめざします。 |
| ⑤ | 母子保護、育児休業、子供の看護休暇など権利行使できる人員配置を求め、制度拡充に取り組みます。 |
| ⑥ | 深夜職場の妊婦、就学前の子を養育する職員の時間外勤務や深夜労働の規制を厳格にし、仕事と家庭を両立できる条件整備を進めます。 |
| ⑦ | 育児・介護法の改正を求め、臨時・非常勤・パート職員の適用を拡充させる取り組を進めます。 |
3 「能力・成果主義」強化反対、「人事制度」改善の取組み
公務員制度改革の柱として能力・成績主義に基づく人事管理制度が強化されています。
08人事院勧告でも今秋からの人事評価制度の試行を前にして、給与法に昇給・一時金の勤務成績のリンクを法制化する勧告を行うとともに人事・給与に「人事評価制度及び評価制度の活用の基本的枠組み」の報告を行っています。
能力成績主義人事制度の強化は公務労働の否定と上意下達の職場支配を強めることに繋がることは明らかです。
自治労連方針を踏まえ、成績主義強化、人事制度改悪に反対し、民主的人事制度改善に向け取組みを進めます。
| ① | ILO勧告に基づく徹底した労使交渉の実施を求めます。 |
| ② | 「査定」昇給など人事評価制度の問題点を整理し、職場学習・討議を進めます。 |
| ③ | 人事考課制度の抜本的改善、民主的人事制度改善にむけ都庁職・都労連と連携し取り組みを進めます。とりわけ、現業人事給与制度の改善に向け取り組みます。 |
4 都政リストラ反対、予算人員要求実現の取組み
08年7月31日、当局による予算・人員に関わる(依命通達)説明では、法人事業税の暫定措置による税収減が現実のものになり都税収入の減少を覚悟せざるを得ない状況にあるとしている。その中にあっても、将来の東京の継続的発展に不可欠な取組みをすすめるとともに、現在の都民生活を脅かす課題に適時適切に対応していく予算とするとしている。依命通達の2では、職員定数は、行財政改革実行プログラムにおける定数削減目標(3年間で4000人)の着実な達成に向け、組織と定数の一体的管理を推進し、事務事業の見直しや、アウトソーシングの推進など、業務執行方法の改善を進めることにより、削減を図ること。あわせて、業務を着実に遂行する観点から、多様な雇用形態も積極的に活用しながら、スリムで機能性の高い強固な執行体制を構築すること。など8項目の方針を揚げている。また監理団体職員数等調整方針について新たにだされている。
職場では度重なる人員削減により、超過勤務は慢性化し、パソコン業務が増大し、疲労を訴える職員が増えている。長期病欠者の補充がなく超勤を余儀なくされ悪循環となっている。
自治労連都庁職は運動の基調をもとに公務公共の真の姿を恒に見極め、都民サービスを充実し、職員がゆとりと働きがいのある職場をつくるため、アウトソーシングの推進に対し政策を対峙し、東京自治労連の運動に結集し自治体行政の役割を変質させてしまう都政リストラ攻撃に広範な都民と共同して闘います。
| ① | 都民と職員の生活権拡充をめざし、石原都政の政策を広範な都民と連帯した学習・交流を行い旺盛な闘いを展開します。 |
| ② | 都政・予算分析パンフを活用した定期的な学習会を開催します。 |
| ③ | 都労連・都庁職の予算人員要求闘争の闘いを積極的に進めます。 |
5 自治研の取組み
「地方分権改革」「道州制」「小さい自治体切り捨て」など「この国のかたち、国と地方の政府のあり方」を変える動きに対し、自治労連は、「見直そう、問い直そう、地ごとと住民の安全・安心」運動を進め、地方自治の拡充や地方財政の確立にむけ幅広い住民との共同を広げています。
6月に行われた第7回東京自治研集会は、「改憲」と「構造改革」路線の先兵としての役割を果たす石原都政の実態を浮き彫りにしました。
自治労連都庁職は、仕事を通じて住民に奉仕する自治体労働者の役割と責任を明確にし、都政リストラに対抗する公務労働・公務サービスの在り方をめざし、職場を基礎とした自治研活動を推進します。
| ① | 支部の自治研活動の取組みへの資料提供、協力・共同する取組みを進めます。 |
| ② | 自治研推進委員会を確立し、自治労連都庁職の交流と研究をすすめ、運動に反映します。 |
| ③ | 東京自治フォーラム、首都圏フォーラムなど東京自治問題研究所の学習会・討論に参加します。 |
| ④ | 第51回自治体学校(09年7月埼玉)などの自治研活動への参加を広げます。 |
6 制度政策要求実現の取組み
| ① | 「消費税増税反対」の世論を草の根で広げるため、消費税の本質を明らかにする学習・宣伝・署名を進めます。大企業などへの適正な課税強化と公的責任を求める取組みを進めます。 |
| ② | 憲法25条にもとづく権利としての社会保障の発展をめざし、ナショナルミニマムの底上げと公的責任を明確にする運動を進めます。安心して住み続けられる保健・医療・介護・福祉の地域ネットワーク確立にむけた取組みを行います。 |
| ③ | 医療制度改悪に反対し、医師・看護師不足の解消や国保制度の充実をめざします。「健康自己責任論」による公衆衛生に対する公的責任の後退を許さない運動を住民とともに進めます。後期高齢者医療制度について、参議院での4野党で可決した法案を衆議院でも可決成立するため奮闘します。 |
| ④ | 深刻な無年金・低年金者の増大、国民年金の空洞化などの根本問題を解決するために、消費税によらない全額国庫負担による最低保障年金制度の確立をめざす運動に取組みます。雇用保険について失業等給付の国庫負担(現行25%)の引き下げを許さない運動にとりくみます。 |
| ⑤ | 生活保護制度の改悪を許さず、改善・充実をめざします。介護制度の抜本改善の運動を強め、誰もが安心できる介護保障をめざします。障害者自立支援法を見直させる運動をすすめ、障害者福祉・医療政策の改善・充実をめざします。子どもの権利条約を生かし、子どもの豊かな成長・発達を保障するとりくみをすすめます。 |
自治労連都庁職は、対都の取組みを以下の点ですすめます。
| ① | 東京都における削られた福祉施策を復元させ、都の公的責任と制度の改善を進める運動をとりくみます。 |
| ② | 次世代育成支援行動計画に関わり、東京都の責任で施策を充実させることをめざします。都庁労働者が仕事と子育てを両立できるための「東京都特定事業主行動計画」の事業主責任を明確にし、「推進委員会」に労働者代表を入れるなど計画の充実を求めます。 |
| ③ | 地域経済の振興・地域雇用確保の施策充実のとりくみを進めます。 |
| ④ | 食の安全と農業・環境保全・災害対策など、安心して暮らせる地域社会の構築をめざします。東京災対連の提起を受け止め、災害対策の強化・三宅島島民支援など取組みを進めます。 |
7 09国民春闘の取組み
08春闘は、原油、小麦、大豆と世界的な原材料高を受けて食料品やガソリンなど生活必需品を中心とした物価値上げが相次ぐ中で、多くの国民・労働者が生活の切り詰めを余儀なくされています。総務省が発表した労働力調査によると、派遣・契約社員、パート・アルバイトなど非正規雇用が占める割合が07年の平均33.5%(前年比0.5ポイント上)と過去最高を記録しました。このような状況の中で、「ワーキングプア」「偽装請負・違法派遣」「名ばかり管理職」「時給1,000円以上」など「格差と貧困の是正」が急速に社会問題化し、国民犠牲の政治の実態が一挙に顕在化しました。
これに対して第一に、資本金10億円以上の大企業は6年連続の史上空前の利益を上げています。01年から5年間で経常利益は、15兆3千億円から32兆8千億円と倍以上の伸びとなっています。第二に、大企業は人件費コストを削減し続けてきました。同時期人件費は50兆2千億円から48兆4千億円へと1兆7千億円以上も減らされています。労働分配率は5年間に60.0%から52.3%に激減しています。第三に、自公政権の大企業奉仕政策の下で、大企業は大減税で恩恵を受ける一方、労働者は低率減税廃止などの増税で家計が火の車になっています。
08春闘の結果、人事院の勧告では、月例給・特別給とも改定見送りとなり、春闘時期の民間の賃金引上げさえも無視された不当な勧告となっています。
09春闘では、全労連・地方労連・地域労連に結集し、引き続き大企業の社会的責任を追及し地域から世論を帰る運動を積み上げ、「最賃」「均等待遇」「公契約」を一体的にたたかうことが求められています。
| ① | 「企業の社会的責任」を追求する大運動を広げ、国民世論を結集し、「企業間格差」など賃金個別化、・春闘解体を許さず09国民春闘をたたかいます。 |
| ② | 空前の利益に対して「労働分配率の是正」を軸にすえ、「大企業の社会的責任」を追求します。すべての労働者に賃上げが保障される「誰でも月額○○万円以上、時間給○○円以上」を掲げ、法定最賃闘争、均等待遇、公契約運動などの賃金底上げ要求の実現を求め、全労連「企業通信簿」など官民共同の中央、地方で広げとりくみをすすめます。 |
| ③ | 青年の雇用問題については、国に対して非正規労働者を重視した正規雇用への転換と雇用安定の政策の実施、自治体に対して地域の雇用・失業対策の積極的支援策、大企業等に対して正規職員の雇用拡大などで社会的責任を果たすことを求めます。 |
| ④ | 09春闘方針は、この秋季年末闘争を継続発展させ、「春闘討論集会」(12月4日~5日)で論議を深め、第○○回中央委員会(09年○月○日~○月○日)で確定します。 |
また、09春闘アンケートは、要求を職場から練り上げていく運動として重視し、全労連の提起を踏まえ組織人員を上回る目標で取組みます。
自治労連都庁職は、この提起を踏まえ、次の点を基本にとりくみを進めます。
| ① | 東京の民間労働者の春闘激励行動など官・民一体の春闘、行動行動の参加、自治労連都道府県職との情報交換を追求します。 |
| ② | 都庁職に働く関連労働者の賃金底上げ、労働条件改善の要求にむけて都庁職関連法人一般労働組合と連携・共同したとりくみを進めます。 |
| ③ | 春闘討論集会への参加、学習会の開催、職場討議の促進、春闘情報提供を迅速に行います。 |
| ④ | 09春闘アンケートを早期にとりくみ、要求への反映・職場討議などに活用できるようにします。 |
| ⑤ | 09春闘方針は別途提起し、産別の要求と課題を明確にして東京都知事あて春闘要求を提出します。産別要求として都庁職、都労連に要請し、対都賃金・労働条件改善に取組みます。 |
8 憲法改悪阻止、改悪教育基本法の具体化に反対し、平和と民主主義・基本的人権を守る闘い
(1)憲法を守るたたかい
| ① | 憲法改正の手続き法が成立したもとで、国民投票法が施行される2年後2010年を見通し、改憲反対の多数世論を作るため、憲法改悪を許さないとりくみをすすめます。 |
| ② | 「憲法9条を守ろう」の国民的な大運動を広げるために、職場・地域の隅々から共同行動をすすめます。職場9条の会、憲法をいかす自治体労働者東京連絡会、自治体9条の会で積極的役割を果たします。 |
| ③ | 職場懇談会などを重視し、憲法学習をすすめます。地域9条の会とも連携し、憲法改悪共同センターの「9の日行動」の宣伝活動や憲法9条を守る国民過半数署名など共同行動をすすめます。 |
| ④ | 「第4回憲法闘争交流集会」(12月5日)、「憲法集会」(5月3日)や「憲法改悪に反対する東京共同センター」の諸行動・集会に参加し、成功をめざします。 |
(2)有事法制の具体化を阻止し、平和を求めるたたかい
| ① | 「東京都国民保護計画」の作成、「東京都国民保護協会」の設置など、有事法制具体化を阻止するため、庁内外の世論づくりと東京都への働きかけをすすめます。 |
| ② | 自衛隊の情報保全隊による国民監視をやめさせ、住民の監視を強める、「国民保護計画」の策定や具体化に反対し、有事法制・国民保護法の発動を許さない取組みをすすめます。 |
| ③ | 自衛隊や警察が参加する有事訓練強化に反対します。 |
「テロ対策特別措置法」の廃止をめざします。
| ④ | 解釈改憲をすすめ、恒常的な自衛隊の海外派兵や武力行使を可能とする「海外派兵恒久法案制定などの動きに対し、全労連の学習リーフの活用、「名古屋高裁判決」の学習と活用をすすめ、署名や宣伝に取組みます。 |
| ⑤ | 世界中からテロと戦争をなくすため、国連憲章にもとづく「平和のルール」を遵守するよう求め、「日米安保条約」の破棄を要求してとりくみます。 |
| ⑥ | 沖縄・名護の新米軍基地建設反対、在日米軍再編強化反対、米軍の世界戦略と一体となる「新世紀の日米新同盟」反対、横田基地をはじめ、すべての日本の米軍基地撤去を求めて運動します。 |
| ⑦ | 放射能汚染を引き起こす、米軍の原子力艦船の日本寄港に反対します。 |
| ⑧ | 2008年日本平和大会(11月13日~15日 神奈川)への参加を強めます。 |
| ⑦ | 「いま、核兵器の廃絶を!」署名に旺盛に取組みます。各地域でとりくまれる「6・9行動」などの宣伝行動に積極的に参加します。 |
| ⑧ | 3.1ビキニデー、2009年原水禁世界大会、国民平和大行進のとりくみを強めます。 |
(3)教育基本法、民主主義と人権を守るたたかい
| ① | 各支部とも協力し、教育基本法の改悪、教育三法の改悪を現場に持ち込ませないための共同のとりくみをすすめます。また、「日の丸君が代」の強制を許さず、「新しい歴史教科書をつくる会」教科書選定に反対し、競争と管理を強化する「教育改革」に反対し、ゆきとどいた民主教育を求めてとりくみます。 |
| ② | 日の丸・君が代強制反対、教職員に対する不当処分反対の取組みをすすめます。 |
| ③ | 表現の自由や思想信条の自由を抑圧するあらゆる動き、特に公務員の自由を奪う動きに反対し、「共謀罪」成立阻止の運動を強めます。 |
| ④ | 石原都知事が人権侵害発言を繰返しているもとで女性や障害者はじめ全ての人の人権を守ってたたかいます。 |
| ⑤ | 企業団体献金禁止や、政党助成金の廃止を求めてたたかいます。 |
| ⑥ | 子どもの人権を守る社会のルールを確立し、子どもの権利条約「子どもの最善の利益」を追求して、国・自治体の子どもの支援・相談の体制の充実を求めてとりくみます。また、世界の大勢である18歳選挙権の実現にむけとりくみます。 |
| ⑦ | 従軍「慰安婦」問題について、「軍の強制は無かった」等の発言を繰返す政府高官に歴史の事実を認めさせ、日本政府に反省と謝罪・真の解決を求める共同のとりくみをおこないます。 |
9 憲法が生きる都民本位の民主的自治体建設・国政革新をめざして
(1)民主的自治体建設・国政革新の取組み
| ① | 石原都政の都民犠牲の施策について明らかにし、都民向け公約を反故にさせない全都的な闘いの継続に貢献するとともに、2009年都議会議員選挙に際しては、私たちの要求や都民要求実現をともに進める勢力の躍進をめざします。 |
| ② | 選挙に当たっては、組合員の政党支持、政治活動の自由を保障しながら、憲法改悪や「小さな政府」に反対し、住民が主人公の地方自治体建設に向けて奮闘します。 |
| ③ | 地方自治を守るため、「地方行革」の押し付けや「行革推進法」の発動を許さないとりくみを進めます。 |
| ④ | 指定管理者制度・市場化テストなど自治体「リストラ」について学習を強め、「市場化テスト法」を市町村に導入させないとりくみをすすめます。また、住民と共同し、保育所・学校給食・病院、文化・教育施設などの独法化・営利企業の参入・民営化に反対します。 |
| ⑤ | 住民と共同し、住民のいのちとくらしを守る自治体本来の役割放棄を許さず、自治研活動をすすめます。 |
| ⑥ | 新たな市町村合併のおしつけや中央集権を進める道州制導入に反対します。また、市町村合併による労働条件変更などの点検を行い、安心して働き続けられる職場にするために取り組みます。 |
| ⑦ | 「地方分権改革」に連動した地方交付税制度改悪に反対し、「財政健全化法」による総務省などの地方自治への介入を許さず、地方自治・地方財政を守るため、学習をすすめます。 |
| ⑧ | 「格差社会」「構造改革」の流れを変える運動として、地域住民の要求と自治体労働者の要求をむすびつけた「1自治体1共同」の運動を、基本組織とともに具体化します。 |
| ⑨ | 「こんな地域と日本をつくりたい」の要求を職場・地域で語り合い広げながら、住民が主人公の民主自治体をつくるために奮闘します。今日的な視点に立って「自治体労働者論」を輝かせるために学習・討論をすすめます。 |
| ⑩ | 企業団体献金禁止や、政党助成金の廃止を求めてたたかいます。 |
(2)公務員の政治活動など権利抑制を許さないとりくみ
| ① | 国公法弾圧掘越事件の高裁での勝利解決をめざすとりくみを強めます。 |
| ② | 時間内組合活動の縮小・廃止など、組合活動の権利抑制の不当な動きに反対します。 |
| ③ | 労働三権の公務員への適用をめざします。団結権を保障する権利としてILO勧告などが示す国際基準に沿った対応を求め、権利の後退、不当な労使慣行の変更に機敏に対応し、徹底した労使交渉による決着を求めます。 |
| ④ | 自治労連発行の「組合活動の権利入門」を学習資料とし、組合活動の権利についての基礎学習を進めます。 |
10 「元気な職場」を都庁につくり、組織拡大強化をめざす取組み
第30回自治労連定期大会において、「政治的な激変と展望を職場に伝え、元気な職場づくりを」が提起されました。参院選の結果とその後の情勢は、さまざまな分野で国民が現実政治を動かす確信と展望を広げています。しかし自治体職場が権力の末端機構として悪政の推進者となり、総務省の干渉介入が強まり矛盾が集中し、「変化と可能性」を実感できない。現実に賃金削減、民営化攻撃は続き、メンタルヘルス不全も広がっています。その打開のため、第一に職場に大きな情勢の変化を職場に伝え、きめ細かく職場懇談をすすめること、第二に、「私の憲法・みんなの憲法」学習運動などを通じて、自治体と自治体労働者のあり方を語り確信にすること、第三に「だれもが参加しやすい」組合活動のスタイルを工夫することです。そして自治体労働者の要求と住民の利益をともにとらえ、たたかいの軸足を職場だけでなく地域にも広げ、地域に出て主権者である住民とともにすすめることとしています。
東京都庁関連法人一般労働組合と共に、指定管理者制度など「自治体市場化」とのたたかいを組織化に結びつけていく取組みを求められています。 組合民主主義を貫き、元気な活動が職場で見える取組みをします。
| ① | 新採加入・未加入対策・組織率向上を追求します。 |
| ② | 組合活動規制攻撃に対し、労働組合への結集を強めます。 |
| ③ | 自治体業務の市場化攻撃に対しては「直営堅持」を基本に奮闘し、都庁法人と連携し組織化を進めます。 |
| ④ | 医療職場(3支部1法人)100名規模の「看護師のいのちと健康を守るアンケート」を集約し、組織拡大に役立てていきます。 |
| ⑤ | 引き続きメールニュースやホームページの充実を図り、宣伝活動を強化します。 |
以上