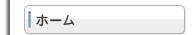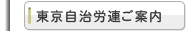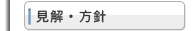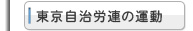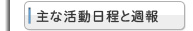東京自治労連2010年度運動方針(案)
はじめに
1.東京自治労連は、都本部機能強化・組織整備以降の7年間の到達点を踏まえて策定された「組織財政見直し方針」を今年度具体化し、組織の強化・拡大を重点課題として取り組みました。
結果としては、まだ先進的な単組の経験ですが、要求と運動の前進を背景に、新規加入組合員数が退職者数を上回り、増勢に転ずるという貴重な成果を生みだし、5万東京自治労連建設へと本格的な歩みを踏み出し始めた1年間となりました。
その要求と運動の前進の具体的事例は、①「現業不補充」方針を打破して、10年ぶりに新規採用を実現、②偽装請負・違法派遣問題での前進的回答の引き出し、③多発した非常勤の雇い止めの阻止・雇用継続などの要求の前進や①保育制度の改悪を許さない取り組みや地域保育政策の提起、②「憲法署名欄付ハガキ」配布や署名集約の前進、③都立病院つぶしへの都民と共同した反撃など運動の前進などがあります。
いまこそ、この組織的前進に確信をもち、今年はすべての単組とその職場での新たな飛躍へと発展させましょう。
2010年度運動方針は、すべての自治体・公務公共関係労働者の賃金引上げ・労働条件改善の闘いと組織強化・拡大の前進を結合させて、すべての単組でいきいきとした組合員の要求に応える活動をめざし、大いに奮闘するための方針です。
2.1)ワーキング・プアなど「貧困と格差」の拡大をもたらした小泉・安倍・福田・麻生の歴代自公政権の「構造改革」政治の失政に対して、2008年暮から2009年新春にかけて国民的にも注目を浴びた「年越し派遣村」などに象徴される「構造改革」路線反対の運動と国民的世論が大きく高揚しました。そして極めて不充分ながら労働者派遣法などが一部見直しされました。そして7月都議選・8月総選挙では自公政権に対して、「NO」という明確な審判が下り、新たな民主党を中心とした政権が誕生しました。
2)いま2010年5月以降、憲法9条改悪をめざす「改憲手続法」発議の策動、道州制移行を展望した第二次「地方分権改革」、公務員制度改革や人事院の役割の再編など文字通り「この国のかたち」を変える新たな「構造改革」が狙われているもとでは、都議選・総選挙後の新たな政治情況をも踏まえれば、全労連、国民大運動実行委員会などの全国規模の運動とともに、東京地評をはじめとする全都規模・首都圏規模での諸団体との共同・運動の一層の前進をはかる必要があります。
3)特に、2010年度運動方針では、これらの要求実現運動とともに、2011年春実施予定の都知事選挙にむけて、現在の大企業優遇・大規模開発優先の都政の方向を、都民本位で、憲法・地方自治がいきづく都政本来の姿に転換させていく本格的準備を行う方針を確立する必要があります。
また、2010年夏の参院選については、組合員の政治活動の自由・政党支持の自由の保障という労働組合の基本原則を堅持し、組合員ならびに国民的要求実現の立場で取り組みます。
3.いま「能力・業績主義」評価と職場管理強化で職場組合員が孤立化し、放置しておけば、「諦め」につながりかねない状況におかれている組合員を励ますため、きめ細かな職場討議・懇談を実施することが重要になっています。
また、「福祉の増進」という自治体の役割への住民からの期待と自治体労働者の任務に立脚し、「官から民へ」という流れ・地方自治の「構造改革」路線に対抗して、すべての自治体・公務公共関係労働者および住民の要求実現とそのあるべき姿・社会的役割について学習活動と住民と共同した闘いが、求められています。
東京自治労連は、「職場の主人公である組合員が誰でも参加できる」労働組合の活動スタイルをしっかりと構築するとともに、自治労連結成20周年記念事業「おきなわプロジェクト」に参加した多くの若者をはじめとする「次世代」の育成へと必ず継承する重要な方針として、2010年度運動方針を提起するものです。
Ⅰ.1年を振り返って
私たちはこの1年間、第20回定期大会で決定された「組織財政見直し方針」に基づく「都本部機能強化」と「組織の強化・拡大」を基本に、運動方針に掲げた諸課題を精力的に取り組んできました。
特に、昨年末以降、私たちの闘いの積み重ねが国民世論を大きく変えて、圧倒的な世論と運動が政府・財界を包囲する劇的な情勢変化を作り出すなかで、多くの具体的な要求実現・運動の大きな前進を築くとともに、5万人東京自治労連建設へむけた組織的前進をも築いています。
この1年間の闘いの到達点と情勢の変化に大きな確信を持って、運動と組織建設を進めていきましょう。
1. 憲法を守り、平和と民主主義をまもる闘い
1)署名を軸とした憲法をまもる闘い
露骨な憲法9条改悪策動が強まるなかで、9条をまもる圧倒的国民世論構築へむけた憲法署名の取り組みの重要性が増しています。
「組合員一人10筆」の目標へむけて、2009春闘における重点課題に位置づけ、第1に各単組における自主的な目標設定と取り組み、第2に組織総体としての目標へむけた具体的接近をめざして、「憲法署名欄付ハガキ」90万枚を作成し、各単組が旺盛な配布行動を展開しました。
世田谷区職労は世田谷九条の会4周年記念講演と音楽のつどい(2/7)、江東区職労のライフ&ピースIN江東憲法のつどい(2/10)、足立区職労の憲法と平和を考える学習会(2/13)をはじめとして、各単組が職場・地域で大規模な取り組みを展開するとともに、全国一斉9の日宣伝行動(08/12/9)などの統一行動に結集、東京自治労連も月1回の定例駅頭宣伝行動を積み重ねてきました。
こうしたなかで、署名は9月30日現在で45,628筆に到達、ハガキ返信で6,499筆が集約されています。
2)「憲法をいかす自治体労働者東京連絡会」の取り組み
「憲法をいかす自治体労働者東京連絡会」は、昨年11月21日に第4回総会を迎えました。
事務局を担う東京自治労連は、憲法擁護の一致点で都内自治体労働者・労働組合が結集する組織としての発展をめざし、品川正治さんを招いた5.25自治体労働者憲法講演会(13単組78名)の成功へ全力を尽くすとともに、11月27日の第5回総会へむけて加盟組織の拡大、加盟組織間意志統一強化へむけた世話人拡大へ全力で取り組んでいます。
3)核兵器を廃絶し軍備拡張に反対する取り組み
核兵器廃絶を中心に据えた平和をまもる取り組みでは、「日本平和大会」「3.1ビキニデー」「国民平和大行進」「原水禁世界大会」などに単組とともに積極的に参加してきました。
また、自治労連都職労再雇用非常勤協議会との共催で、3月19日には憲法講演会「イラク派兵違憲判決から見えてくること」を57名の参加で成功させてきました。
いま2010年5月のNPT再検討会議へむけて、新国際署名「核兵器のない世界を」の具体的推進を含めた行動計画の策定準備を進めています。
2.賃金・労働条件の改善、「働くルール」の確立をめざして
1)2009春闘
2009春闘は、「2009年国民春闘働くみんなのアンケート」による要求集約と、127名の参加による春闘討論集会(08/12/12-13)における方針素案討議でスタートし、組合員が主体的に参加した「年越し派遣村」(08/12/31-1/5)が政治と行政を大きく動かして情勢の大きな進展を築くなかで、「情勢の進展を受けた09春闘期の新たな課題と取組について」を含めた「2009年国民春闘方針」、「同基本要求」を第34回中央委員会(1/24)で確立して闘ってきました。
闘う体制の確立へむけて重視したストライキ批准投票では、全単組の実施と昨年を上回る批准率を目標として意思統一し(1/19、第2回拡大中執「2009年ストライキ批准投票の成功へ向けて」)、全単組の取り組みで76.38%の高率で批准しました。
方針・要求・体制を確立して、3.12全国統一行動を14単組6組織1,341名の参加で成功させるとともに、国民要求実現2.13中央総行動、09春闘勝利3.5中央行動、公務労組連絡会4.22中央総行動の各中央行動を拡大中央執行委員会における意志統一の下に取り組みました。
1月28日から取り組まれた東京春闘共闘の自治体キャラバンには、自治体直接雇用非正規職員の労働諸条件改善や公契約問題など東京自治労連の重点要求課題が位置づけられていることを踏まえて、主体的な参加を重視して方針確立・単組との意志統一で取り組みました。(1/19、第2回拡大中執「2009年自治体キャラバンの成功へ向けて」)
春闘要求は、各単組が基本要求を踏まえてそれぞれ要求書を提出するとともに、2月9日第3回拡大中央執行委員会において、対都・市長会・町村会宛「東京自治労連2009年国民春闘要求書」を決定し、2月27日市長会・町村会、3月16日東京都へ要求書提出・要請行動を実施しました。
春闘全体は、「賃上げも、雇用も」という圧倒的な国民世論を背景に、連合は8年ぶりにベア要求を掲げたものの、莫大な内部留保を有する大企業がべアゼロ、一時金も要求を大幅に下回る回答を提示し、連合傘下の大企業労組が闘わずして受け入れるという事態の下で、国民春闘共闘委員会最終集計においても5,926円(1.94%)で「定期昇給分をほぼ確保」という全体としては厳しい結果となっています。
しかし、東京自治労連は、各単組の奮闘のなかで、直接雇用非正規職員の大幅賃上げ・諸権利改善、非正規・公務公共関係労働者の解雇撤回や雇用問題改善、介護従事労働者の処遇改善、墨田区職労における10年ぶりの現業職員新規採用実現や委託事業(住民票等郵送請求事務)の直営復元の実現など全国的にも極めて高い到達点を確保しました。
また、都当局を追い込んだ都立3小児病院廃止条例反対闘争、地域の保育・子育て支援政策づくり運動をはじめ、運動においても大きな前進を築きました。
要求実現・運動前進の教訓は、第一に、官製ワーキングプア・介護従事者処遇問題・地域医療・子育て支援など社会的世論を背景とした積極的な運動、制度改善や省庁交渉到達点を具体的運動で職場における要求前進につなげていること。第二に、非正規問題における正規・非正規の共同闘争、地域・利用者との大きな共同の取り組みが運動・要求の前進を導いていることです。
2)労働法制改善、雇用確保・生活危機打開へむけた闘い
「派遣切り」に象徴される大量の非正規労働者の解雇と、解雇と同時に生活困窮状態に陥る低賃金の実態に対し、「生活危機打開へ向けた対応の具体化について」を決定(08/12/17中執)し、各団体の「雇用とくらしの相談会」支援や東京社会保障推進協議会発行ハンドブック編集にも主体的にかかわり、各自治体当局宛「地域住民の生活危機打開へ向けた緊急要請書」(1/7中執)を策定するなど自治体労働組合としての役割を踏まえた取り組みを進めました。
特に、首都圏青年ユニオン(公務公共一般青年支部)も主体的に担った「年越し派遣村」(08/12/31-1/5:入村499名、ボランティア1,700名)は、1月2日の厚労省講堂開放にはじまって、政府・自治体の緊急雇用対策、雇用保険法改正(3/19)など政治・行政を動かす闘いにつながりました。
非正規労働者の労組結成・加入が相次ぎ、派遣切りに対する闘いが労働者派遣法抜本改正を求める運動につながり、東京自治労連も「労働者派遣法の抜本改正を求める全国集会(08/12/4、2,000名),「労働者派遣法の抜本改正を求める5.14日比谷集会」(1,000名)などの中央行動に結集するとともに、産別組織の違いを超えて開催された「なくそう!官製ワーキングプア~反貧困フェスタ」(4/26、430名)に主体的に参加するなど運動が前進しています。
こうした流れのなかで、労働基準法改正(08/12/5)、育児・介護休業法改正(6/24)など労働法制面での前進が築かれています。
3)最低賃金引き上げ闘争
解雇と同時に生活困窮状態に陥る深刻な低賃金構造のなかで、最賃の大幅引き上げが重要であり、「生活保護との整合性確保」を明記した最低賃金法改正の趣旨に基づく速やかな改善が必要です。特に、春闘結果や公務員の一時金一部凍結問題など財界の人件費抑制攻撃を踏まえて、「最低賃金・09人事院勧告を中心とした夏季賃金闘争の推進へ向けて」(6/8拡大中執)を決定し、全力で取り組んできました。
5月15日・6月30日・7月23日の各中央行動に結集するとともに、東京地評に結集し、都最賃審議会に対する闘いにおいても先頭に立って奮闘しました。
7月29日に、中央最賃審議会は、「生活保護基準を下回る12都道府県に限定して2~30円引き上げ、他35県は経済情勢悪化を理由に据え置き」という極めて不当な改定目安額答申を強行し、全国平均引き上げ額は7~9円、前年度の16円から大幅な後退を強要しました。
これを受けた、都最賃審議会は、8月5日に25円増の791円を答申しました。昨年の27円を下回るとともに、中央最賃審議会改定目安額答申が示した「20~30円」に対しても、不当な低額水準です。直ちに異議申立書を東京労働局長に集中しましたが、8月21日の異議申出審議を経て、10月1日発効が決定されており、引き続く闘いの強化が求められています。
4)公契約闘争の推進へむけて
この間東京土建との定期協議を重ねてきていますが、実効ある共同闘争の展開を目的として、両組織の重点課題でもある公契約条例制定運動の具体化問題で実務者協議を設置しました。
このなかで、「『東京都入札契約制度改革研究会第一次提言』に対する見解と意見について」(3/25中執)を合同で策定し、都当局へ提出するなど具体的前進がありました。
5月13日には、「公共サービス基本法」が全会一致で可決されており、同法11条(労働条項)の具体化を自治体当局に要求する闘いへむけて、制度政策要求と地域労組との共同の具体化と方針確立を急いでいます。
3.自治体・公務公共関係労働者の賃金労働条件改善へむけた闘い
1)2008賃金確定闘争
2008賃金確定闘争は、基本給・一時金ともに据え置く2年ぶりの人事院「ゼロ勧告」を受けて、特別区人事委員会も据え置き勧告を行い、全体として厳しい闘いとなりました。
特に、都人事委員会が、道理も説得力もない極めて政治的なマイナス勧告を強行するにとどまらず、現業賃金水準の見直しまで言及したため、東京都内の確定闘争は、極めて厳しい闘いを余儀なくされました。
東京自治労連は、交渉組織である都労連・特区連の闘いに主体的に結集するとともに、三多摩地域の各単組への情報提供などに努めました。また、「不当な東京都人事委員会勧告に抗議し、都職員のたたかいに連帯する民間単産アピール~民間30単産委員長名(08/11/6)」に象徴される東京地評を軸とした官民共同の取り組みを推進しました。
組合員の団結と闘いで、都における最大の焦点であった現業賃金改悪問題では、当初提案の△15%を△8%まで押し返し、号給足のばしなどの到達点を築いています。
2)2009夏季一時金一部凍結問題
総選挙を前にした与党の政治的思惑に人事院が追随し、公務員の夏季一時金0.2月を暫定的に凍結する特例措置勧告が強行されました。
①精確性・妥当性を欠くもの、②政治的利用への追随、人事院の役割放棄、③民間春闘・一時金の押さえ込み、④賃金決定ルール蹂躙という問題点を組合員に明らかにして、精力的な取り組みを展開しました。
夏季一時金削減反対人事院前緊急要請行動(4/28)をはじめとした中央行動に参加し、東京地評主催の人事院及び都・特別区人事委員会要請や人事院前緊急要請行動(4/24)などに全力で取り組みました。
結果は、極めて強い地方統制のなかで、5月25日特区連、5月26日都労連をはじめ0.2ヶ月凍結を余儀なくされており、人勧体制に基づく不当な賃金抑制システムの問題点が改めて鮮明となりました。
3)自治体直接雇用非正規職員の賃金・労働条件改善闘争
人事院「非常勤職員に対する給与指針」、改正パート労働法施行、最賃引き上げを踏まえて、臨時・非常勤職員など直接雇用非正規職員の劣悪な賃金・労働諸条件の抜本的な改善を2008秋季年末闘争から2009春闘期の重点課題として位置づけ、昨年12月1日の第1回拡大中央執行委員会「自治体直接雇用非正規職員の賃金改善へ向けた当面の取り組み方針」を決定し、正規・非正規共同の闘いを提起しました。
直接雇用非正規職員賃金闘争学習交流集会(08/12/10)を23単組・局支部51名の参加で成功させ、墨田・江東区職労における正規・非正規合同決起集会開催など各単組の旺盛な闘いが展開されました。
4月24日には、13単組局支部40名の参加で直接雇用非正規職員雇用・賃金改善闘争中間総括集会を開催し、闘いの到達点を交流しましたが、文京区平均7.8%、世田谷区・目黒区平均3.6%をはじめ大幅な賃上げを多数の自治体で実現するとともに、休暇制度改善など労働諸条件も前進し、極めて大きな到達点を確保しました。
4)非正規・公務公共関係労働者の雇用確保の闘い
「派遣切り」に象徴される雇用破壊攻撃は、自治体・公務公共関係の職場にも同様に現れ、公務公共一般労組は、例年以上に多数の解雇問題を抱えて2008年度末闘争を闘いました。
2法人で50名という大量解雇と闘った多摩支部、財団法人における「雇い止め」攻撃に対し闘い、組織を大きく拡大した世田谷支部をはじめ当該組合員・単組の精力的な闘いと正規・非正規一体の闘いで、多くの解雇撤回を実現しました。
また、解雇反対の闘いにとどまらず、江東区における学童保育クラブ非常勤指導員4年有期雇用撤廃、中央区非常勤職員の「5年雇い止め」問題での再公募確保など雇用年限問題での要求前進も多数獲得しています。
都専務的非常勤職員への「5年雇い止め」導入問題では、東京自治労連は「当面の闘争方針」(08/12/3中執)を確立して、都労委闘争を展開していますが、総務省が、「『更新への期待権』が発生しない任用管理」を強調する公務員課長通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」を4月24日付で通知した下で、非正規職員の雇用と労働条件に対する改悪攻撃が更に強まることも想定されます。
都内自治体に多い雇用更新回数限度設定は、総務省通知の中でも否定されており、雇用年限撤廃闘争を対置した闘いを強化する必要があります。
5)労働時間問題への対応
2008人事院勧告において、勤務時間週38時間45分へ1日15分短縮することが勧告されました。
これを踏まえて、特別区等は今年度から勤務時間短縮が実現していますが、都においては、不当にも「引き続き協議」の扱いとされ、勤務時間短縮が先送りされており、早期実施をめざす闘いの強化が必要です。
特別区において、国が交替制勤務職場の休息時間を存置するにも関わらず、休息時間全廃を提案してくるなかで、各区・市の労使交渉へむけて、東京自治労連として「交替制等勤務職場の休息時間問題について」(2008/12/17中執)を決定し、対応を意志統一しましたが、残念ながら全廃に至っており、引き続き国の対応を踏まえた制度改善が課題となっています。
過重労働問題と不払残業問題は引き続き、重要かつ緊急の課題となっています。不払残業問題では、自治労連都庁職教育庁支部坂本さんの裁判闘争を軸として、当該単組とともに、都庁全体の不払残業一掃・過重労働解消へむけた闘いの一環として奮闘しています。
6)労働安全衛生活動
だれもが健康で働き続けられる職場づくりは、自治体「構造改革」攻撃の嵐のなかで、組合員の最も切実な要求課題となっています。
「2009年労働安全衛生活動取組方針」(2/25中執)を確立し、単組代表を含めた労働安全衛生活動推進委員会を中心に、取り組みを進めてきました。
推進委員会には、6月の11単組1組織16名をはじめ多くの単組から委員が参加して、2007年健康アンケート集計結果も踏まえ、実効あるメンタルヘルス対策・非正規職員の労働安全衛生などを主要課題に位置づけて9月26日に実施した第8回労働安全衛生活動交流集会も154名の参加で大きく成功しました。
7)2009賃金確定闘争
一時金一部凍結を受けて、2009人事院勧告に対する闘いは組合員の生活と不況のもとでの国民生活・地域経済にとっても重要な課題です。
「最低賃金・09人事院勧告を中心とした夏季賃金闘争の推進へ向けて」(6/8中執)に基づき、最賃問題と結合して人勧期の闘いを展開しました。5.15最賃・人勧デー中央行動、公・民賃下げサイクル阻止!7.17人事院前行動、09夏季闘争勝利7.23中央行動などの諸集会、人事院関東事務局要請(自治労連関東甲越ブロック主催)・人事院要請行動(東京地評公務部会主催)などの要請行動に全力で取り組むとともに、人事院宛個人・団体要請署名の取り組みでは、個人13775名、178団体という高い到達点を確保しました。
しかし、8月11日の人事院勧告は、月例給で△0.22%(△863円)、一時金は過去最大の削減となる△0.35月(4.15月)職員に平均15万4千円の年間給与削減を強要する史上最悪水準の勧告が強行されました。
即日、勧告内容説明会を2会場で開催し、65名の参加で勧告概要と問題点を確認するとともに、各単組での時間外報告集会を実施し、組合員にその不当性を明らかにしました。
さらに、政府が、総選挙目当てに投票日直前の8月25日の閣議において人事院勧告の取扱を決定する動きを示したため、政府宛緊急要請書提出の取り組みを短期間に集中しましたが、勧告どおりの実施が閣議決定され、同日付で地方人事委員会勧告と地方確定闘争への不当な介入を内容とした総務事務次官通知が送付されました。
これを受けて、本格的な地方確定闘争へ入ります。
4 自治体「構造改革」に反対し、地方自治をまもり発展させる闘い
1)民間委託問題への対応
業務の民間委託攻撃は定数抑制方針のもとで強まっており、特に現業職員の「退職不補充」方針を背景とした現業職場の民間委託が加速しています。
一方で偽装請負・違法派遣が社会問題となり、行政への是正指導も増えており、昨年7月15日に自治労連が実施した学校給食の偽装請負問題での厚労省交渉などにおいて、給食調理業務委託にかかわって従来よりも明確な労働局回答が引き出されるなど状況も大きく変化しています。
こうした状況の変化を踏まえ、偽装請負問題を重視し、新規委託化や委託拡大を阻止していくことを目的として、「調理・用務職の偽装請負問題対策会議」を設置(2008/11/12中執)し、単組役員とともに東京労働局要請を準備してきました。東京労働局宛「自治体における調理・用務業務の委託問題に関わる質問書」を決定し、3月19日に現場代表を含む28名で東京労働局要請行動を実施し、当局が絶対視する委託仕様書そのものに偽装請負と指摘される部分が多く含まれることを明らかにしました。
その後、従来は曖昧であった点について明確な考え方を打ち出した3月31日付厚労省疑義応答集が発行され、これを踏まえた自治労連本部の学習パンフレット作成に主体的に参加し、パンフを踏まえた自治体職場における偽装請負・違法派遣問題学習会(6/17、45名)を開催、今後の闘いへむけて6月24日付で闘争方針「自治体職場からの偽装請負・違法派遣の一掃へ向けて」を確立しました。
このなかで、各単組の闘いも前進し、保育園調理委託問題で目黒区職労が区内3箇所で「保育園給食まつり」開催、学校用務委託提案に対する板橋区職労の全戸宣伝などに加え、墨田区職労が、①10年ぶりの現業職員新規採用(土木現業)②民間委託されていた住民票等郵送請求業務の直営復元という全国的にも極めて高い到達点を実現しています。
こうした到達点を踏まえて、今秋季年末闘争での大きな前進をめざして闘いを進めています。
2)地方自治・自治研活動
総務省が、2月13日住民基本台帳ネットワークに接続していない国立市に対して是正要求を行うよう東京都に指示し、これを受けた都当局が、16日に是正要求書を国立市に提出しました。地方自治を否定するこの措置に対して、「総務省による国立市に対する住基ネット接続を求める是正要求に対する見解」(2/18中執)を発表しました。
また、昨年12月8日に示された地方分権改革推進委員会第2次勧告に対しては、分権の名のもとに住民生活破壊をもたらす国による「義務付け・枠付け」の全面的な廃止・見直しが示されたことを重視し、「地方分権改革推進委員会第2次勧告検証運動についての取組方針」(4/6第5回拡大中執)を確立し、対応を進めています。
この取り組みを踏まえて、自治体行財政委員会において、地方分権改革推進委員会第2次勧告検証と都区制度改革をテーマとしたブックレット作成を準備しています。
財界が「究極の構造改革」と位置づけ導入へむけた対応を加速している道州制問題をはじめ、「分権改革」問題など地方自治に関わる各種学習会並びに第51回自治体学校in埼玉などに積極的に参加してきました。
また電子自治体対策委員会は、電子カルテ問題などをテーマに3回のフォーラムを実施、まちづくり学習交流会は、まちづくり協議会準備会を発足させるなど発展しています。
3)都政問題
対都要求交渉を担う都民生活要求大行動実行委員会、都議会開会日行動をはじめとした対都闘争を担う都民要求実現全都連絡会、革新都政をつくる会については、主体的に役割を担い、諸行動にも積極的に参加してきました。
対都政策活動では、「2008年度東京都税制調査会答申への見解」(08/12/17中執)発表などの対応とともに、本年度も「東京都の予算分析」(3/26)を発行し、組合員の協力を受けて東京都の財政運営・予算編成の問題点を明らかにしました。
7月12日投票の都議会議員選挙に対しては、都政を都民本位に転換していく上での重要性を踏まえ、「都民本位の都政を確立するために都議会議員選挙で奮闘しよう」(6/8第7回拡大中執)を決定し、要求闘争の一環として主体的な対応を打ち出しました。
具体的には、都政・都議会の問題点を広く内外に明らかにしていくことを目的として、10万部の都政問題リーフを発行し、配布・普及活動を展開しました。
都議会議員選挙結果は、自民・公明で過半数割れ、特に自民党は過去最低の議席数に後退し、第二党に転落する劇的な結果となり、都民の自公政権に対する審判・石原都政への不信任を明確に示すものとなりました。
躍進した民主党は、都議会において知事提出議案の99.3%に賛成する実質与党でしたが、選挙戦においては野党的姿勢を示しており、要求実現へむけた大衆運動の強化が今後の大きな課題となります。
4)首長選挙・総選挙
民主的自治体を建設する上で首長選挙は重要です。東京地評や自治労連本部の推薦要請を踏まえて、多くの首長候補の推薦を決定するとともに、都内においては日野市・西東京市・小平市長選挙で東京自治労連統一行動を設定するなど積極的な支援行動を配置しました。また、千葉県知事選挙をはじめとした全国支援行動にも主体的に参加しました。
都議会議員選挙・総選挙を前に「自由に旺盛に展開できる自治体労働者の政治活動・選挙運動学習会」(6/5)を開催し、このなかで東京都安全・安心まちづくり条例改悪問題の学習も位置づけるなど、政治活動はもとより言論・表現の自由をまもり、発展させる立場で対応しました。
総選挙へむけては、「総選挙を闘う東京自治労連の構えと基本要求について」(7/13第8回拡大中執)を確立し、要求闘争の一環として総選挙闘争を位置づけるとともに、組合員の選挙活動の自由を保障して対応を進めてきました。
総選挙結果は、自民・公明が191議席減、民主が193議席増という自・公政権に対する明確な国民の審判が下りました。
国民が作り出した新たな情勢の下で、社会保障・労働法制改善をはじめとした国民要求前進へ向けた闘いの前進をめざすとともに、民主党政策において私たちの要求と相容れない公務公共サービス執行体制や平和問題等における闘いの強化が求められます。
5.社会保障充実、国民生活擁護の闘い
1)公的保育
公立保育園の民営化や保育園業務の民間委託攻撃に加え、公的保育制度の解体攻撃が保育水準を引き下げる最低基準見直し問題とともに重要課題として浮上してきました。
厚労省が、保育における公的責任放棄・市場化を狙う「新たな保育の仕組み」導入へ極めて強引に検討を推し進めるなかで、組織としての重点課題と位置づけて闘いを進めています。
保育制度解体を許すな11.24保育大行動(08/11/24、全体2800名、東京354名)などの中央諸行動に積極的に参加するとともに、「公的保育制度解体攻撃との闘いの強化へ向けて」(1/21中執)、「公的保育制度解体攻撃に対する当面の行動計画について」(4/15中執)など節目毎に独自方針を確立して、主体的な闘いを進めました。
都議会議員選挙前には、広範な都内諸団体との共同で「『守らねば公的保育』5.30東京集会-保育制度改変と東京の保育」(5/30、258名)を成功させ、さらに、自治体に働く保育労働者の春の東京集会(6/7)には19区7市から226名を結集するなど、運動と共同を前進させています。
公的保育制度解体との闘いは、保育園のみならず学童保育問題を含んでいること、組織の重点課題であることを踏まえ、闘争委員会を設置して取り組みを強化しています。
この闘いは、民営化・業務委託攻撃との闘い、認証保育所などの制度問題、待機児解消・子育て支援・児童発達保障などの政策課題とも一体の闘いです。
民営化問題を抱えている墨田・江東・目黒区職労は大きな構えで地域の保育・子育て支援政策づくり運動を展開し、7月に墨田区職労が「すみだの保育・子育て支援政策最終報告書」を発表し、自民党区議団から懇談申し入れを受けるなど、大きな影響を与えています。
公立保育園民営化反対闘争では、国立市職が民営化計画を押し返す大きな到達点を実現しました。昨年12月議会における公立保育園2園の民営化を含む一方的な「財政健全化の方策案」提示に対し、短期間に12,237筆の署名を集約し、3月議会における「民営化を進めないことを求める陳情」の「趣旨採択」を実現し、5月11日の市長と保護者・保育分会との懇談会において、「公立保育園民営化案を一旦取り下げて『今後の保育のあり方についての審議会』で検討」との回答を引き出したものです。
今後、これらの闘いの到達点を全体に共有化し、運動の前進をめざします。
なお、「守ろう子どもの未来、つなごう平和への思い“みんなのつどい2009”」(5/17、400名)、「第41回全国保育合同研究集会」(7/25-27大阪、全体1万人)をはじめとした諸集会にも積極的に参加してきました。
2)医療
昨年12月2日開会の第4回定例都議会において、2009年4月からの地方独立行政法人への移行を前提とした老人医療センター・老人総合研究所の廃止条例が提案されました。
老人医療センター等の地方独立行政法人化問題では、この問題を重視し、当該単組・支部と精力的に取り組んできましたが、廃止条例提案に強く抗議する声明(12/3中執)を発表し、12月4日に緊急の都老人医療センター等の地方独立行政法人化問題都議会各会派要請行動を実施しました。
都立3小児病院廃止問題では、「都立3小児病院廃止条例提案に断固抗議し、存続・拡充を求める当面の取り組みについて」(2/12中執)を決定し、東京自治労連独自に都議会各会派要請行動(2/18)を実施するとともに、都立3小児病院の廃止条例の廃案を求める実行委員会に主体的に結集し、広範な団体・都民との共同闘争を展開しました。
3月11日から24日までの座り込み行動には延べ514名参加、山場となる委員会採決の3月18日の新宿駅西口大演説・都庁周辺デモ行進・座り込み・厚生委員会傍聴行動は延べ1、500名の参加で大きく成功させ、委員会採決で1票差まで都側を追い込みました。
都議会第1回定例会における都立3小児病院廃止条例可決に対しては、抗議声明(4/1中執)を発表し、条例に廃止日が明記されていないことを踏まえた継続闘争を呼びかけ、都立3小児病院の存続、全都立病院の都直営での充実を求める5.16総決起集会(182名参加)を成功させるとともに、都議会議員選挙へむけた都政リーフにもこの問題を大きく位置づけて、都民宣伝を進めてきました。
町田市民病院労組も、公営企業法全部適用問題に対する旺盛な闘いを展開し、広範な市民・団体が結集する「市民のための市民病院を考える会」などの市民との共同闘争を展開し、組織的にも大きな前進を築いています。
3)介護
介護問題では、介護崩壊が社会問題となり、介護報酬引き下げに伴う劣悪な介護労働者の労働条件改善が国民世論となって、介護報酬の初めての引き上げが行われ、これらを踏まえた労働条件改善の具体化が大きな課題となりました。
公務公共一般目黒支部と目黒区職労の共同闘争で、特別養護老人ホームなどを運営する目黒区社会福祉事業団において、非正規職員21名の正規職員化、非正規への一時金導入と報酬月額大幅引き上げなど、全国的にも大きな到達点を実現しました。
介護職場に労働組合を確立し、積極的な闘いの積み重ねによる前進であり、こうした教訓を踏まえて、介護労働者の組織化の前進が求められます。
今年も、介護福祉士試験受験者宣伝行動(1/25、3会場に36名参加、4,400部配布)などの取り組みを展開し、介護労の奮闘によって組織人員が200名を突破する前進を築きました。
また、介護制度の抜本的改善をめざして3月14日には、「介護をよくする東京の会」が結成されており、事務局を担って奮闘しています。
4)後期高齢者医療制度
国民の大きな批判を受ける後期高齢者医療制度問題では、その廃止へむけて「後期高齢者医療制度の廃止を求める東京連絡会」へ主体的に結集して取り組みを進めてきました。
同会の主催した後期高齢者医療制度の廃止を求める東京大集会(08/12/14、全体5,000名、135名参加)、後期高齢者医療制度の廃止を求める6.2集会(550名)を成功させ、都民に大きくアピールしました。この問題では、苦情・問い合わせ件数が対象者の過半数の規模に達する(08/3/1-10/31で都内59万件)など、関係職場職員のたいへんな過重労働の実態も生んでおり、制度の抜本改善と労働条件改善を統一して闘いを強化する必要があります。
5)生活保護
群馬県渋川市の高齢者入所施設「静養ホームたまゆら」で3月19日夜に火災が発生し、10名が死亡するという痛ましい事件が発生しました。入所者の多くは墨田区をはじめとした都内自治体から入所した生活保護受給者でした。
「『静養ホームたまゆら』火災死傷事故に対する見解」(3/25中執)を発表し、問題の本質が「構造改革」路線に基づく社会保障改悪にあり、各福祉事務所における決定的な人員不足にあることを明らかにし、公的介護施設整備や人員増を柱とした生活保護職場の執行体制改善・予算増を強く求めました。
当該単組の墨田区職労は、粘り強い取り組みの中で、5月15日の区長交渉において次年度の増員の方向での検討を約束させています。こうした到達点も踏まえて、「生活保護行政の改善と生活保護職場の大幅な増員を求める取組について」(5/27中執)を確立し、全単組での具体的前進をめざして取り組みを進めています。
制度改善闘争では、「生存権裁判を支える東京連絡会」に主体的に結集し、生存権裁判闘争の支援を進めており、生存権を真に保障しうる生活保護制度の実現をめざして奮闘しています。
6.組織強化拡大
1)拡大中央執行委員会を軸とした本部機能強化
第20回定期大会で決定された「組織財政見直し方針」に基づく「都本部機能強化」の柱として、単組・補助組織・職域部会代表を含めて構成する拡大中央執行委員会を確立し、月1回定期的に開催してきました。
情勢を踏まえた当面の重点課題での意志統一を重視し、毎回40名前後が参加し、東京自治労連運動を本部・単組・補助組織・職域部会が一体となって闘い、運動の展開が強化されています。
2)新規加盟単組拡大
5万人東京自治労連の建設をめざすうえで不可欠な新規加盟単組の拡大へむけて、「新規加盟単組拡大へ向けた2009年度方針」(11/26中執)を確立し、本部の常駐担当者による組織拡大対策会議(19回開催)を踏まえて、具体的で精力的な取り組みを展開してきました。
多くの未加盟単組との日常的な共同関係が確立し、新規加盟単組拡大へむけた土台を築いています。
3)非正規雇用・公務公共関係労働者の組織化
広大な組織化対象である非正規雇用・公務公共関係労働者の組織化を加速していくために、①自治労連の組織化目標を踏まえた東京における組織目標数の設定、②未組織公務公共関係労働者の組織化を加速するための方策、③公務公共関係労働者単組に対する財政支援のあり方を課題とした「関連労働者組織化問題戦略会議」を設置し、精力的な討議を進めてきました。
「関連労働者組織化問題戦略会議中間報告」は4月8日から機関討議に付し、実効ある機関討議を確保するために二重加盟役員懇談会の開催なども配置しながら検討を進めています。
また、具体的な取り組みとして、当面の組織拡大の前進をめざしてリーフレット「公共一般の組合に加入しましょう」を発行し、各単組の協力で大量配布を進めてきました。
こうした取り組みと正規・非正規一体となった要求闘争と要求の実現で、組織拡大も大きく前進しています。
4)春の組織拡大月間の取組
春の組織拡大月間は、3月9日開催の第4回拡大中央執行委員会において「春の組織拡大月間に向けた方針」を決定し、各単組とともに全力で取り組みを進めてきました。
新規採用者の組織化では各単組が創意・工夫のある取り組みを展開、非正規・公務公共関係労働者の要求闘争の前進と結合した組織拡大の取り組みも旺盛に取り組まれ、前年を703名上回る2,531名の拡大という近年にない高い到達点を確保しました。
組織人員総数は、前年比△1,497名ですが、秋の組織拡大月間で増勢に転じる条件をつくり出したものであり、第10回組織集会(7/25)での意志統一を踏まえて一層の前進をめざします。
5)次世代役員育成にむけて
次世代役員育成は、組織の未来にとって重要な課題であり、各単組においても青年組合員の教育や結集へむけた創意ある取り組みが進んでいます。
全体では、自治労連20周年おきなわプロジェクト(6/12-14)に全力で取り組み、東京からも101名の参加を実現、全体で1,267名という画期的な取り組みとなりました。
その規模の画期的さだけでなく、7月22日には東京報告集会を開催しましたが、参加組合員に大きな感動を与えており、継続した対応が重要です。
6)自治労連第31回全国大会の成功へむけた取組
自治労連結成20周年の記念すべき自治労連第31回定期大会が都内で開催されることとなりました。
1月7日に「自治労連第31回定期大会現地実行委員会の設置方針」を決定し、1月19日に各単組・補助組織・職域部会代表を含む第1回現地実行委員会を発足させ、大会成功はもとより、運動と組織の前進で大会を迎えることを意志統一して準備を進めてきました。
総選挙日程との関係で、開催日程・事前会議会場変更、全体日程短縮などがありましたが、4日間で延べ273名の組合員が要員参加、本大会・事前会議の代議員・傍聴参加は572名に達しました。参加者に感動を与えた歓迎行事に55名の組合員が参加するなど、大会の成功へ大きく寄与するとともに、要求・運動・組織の前進で大会を迎えることが出来ました。
7)教宣文化関係
財政事情から、ジョギング・釣りなどの行事を残念ながら廃止しましたが、全国大会出場者選抜を目的とした囲碁・将棋大会(5/16)、野球大会(4/4.5.6)、女子バレーボール大会(7/26)を開催し、多くの組合員の参加を得ました。スポーツ大会を通じた組合員拡大もあるなど組織的にも重要な取り組みとなっています。
同じく財政事情から機関紙発行回数を月1回に縮少しましたが、単組に対する情報提供を補い、強化するためにファックスニュースやホームページ運用を重視して対応してきました。
8)自治労連共済事業
組合加入と共済加入を一体のものとして位置づけた単組が新規採用者の労組加入・共済加入ともに高い到達点を築いており、位置づけの強化が求められています。
自治労連共済東京支部は、自治労連共済20周年の年に過去最高の峰をめざして「春の加入者拡大キャンペーン」、「新人セット共済42型プレゼント」、「新人歓迎ボウリング大会」などの取り組みを行い、4単組で加入実績を上げ、前進しました。
都区職員共済会も来年12月に20周年を控え、各職場での加入者数目標を設定して、セット共済を軸とした加入促進へむけ09年度新採・青年加入キャンペーン(4-7月)を展開し、新規採用者1,971名中で360人加入、未加入者の組合新規加入と合わせて366名の共済加入を実現する高い到達点を築いています。
また自治労連共済東京支部の結成10周年記念レセプションが、7月25日東京自治労連第10回組織集会終了後に開催され、自治労連共済の拡大の意義を確認し合う場となりました。
Ⅱ.私たちを取り巻く情勢の特徴
1.自治体「構造改革」の下で荒廃する職場と労働者
自治体「構造改革」は国民・都民生活だけでなく、私たち自治体・公務公共関係労働者と職場に対しても深刻な被害を及ぼしました。過度な職員定数削減に加えて、「民間にできることは民間で」の掛け声に基づきアウトソーシングが急速に進み、専門性に裏打ちされた技術の継承は著しく低下してしまいました。また、仕事の忙しさと同時に「能力・成果主義」的人事制度の導入強化により、労働者の「やる気の喪失」をはじめとした職場の荒廃も深刻な状況となっています。
東京自治労連の「09春闘アンケート」では、専門職では「やりがいがある」と答えた組合員が80%から90%に達することが多い一方で、事務職では65%にとどまるという結果が出ています。
都政新報(2009年4月14日付)によれば「技術を捨て、現場を斬り、頭でっかちな事務管理の部門だけを巨大化させ」(本庁課長)、「会議はもはやなく、報告と伝達の会だけだ」(本庁部長)、「職員は疲弊し、ついに疲弊がトレンドになってしまった」(出先部長)。石原都政を支えているはずの幹部でさえ、こうした感想を述べているのですから、最先端で住民生活の向上を目指して奮闘している一般職員には職場の矛盾は一層深刻です。
メンタルヘルスも大変増えています。都総務局発表『安全衛生管理の状況』(平成19年度版)によれば、「30日以上病気休暇等の理由」として「精神障害」が引き続き第1位と、全体の53.3%、第2位の「新生物」の4倍となっています。他の自治体でも同様の職場実態が存在しています。
自治労連はこうした実態を改善するために、「見直そう、問い直そう!職場と仕事」の運動を提唱し、徹底的な検証とこれに基づく取り組みを展開してきました。東京自治労連も自治研活動や労働安全衛生活動を中心に据えて、仕事と職場を見直す取り組みを進めてきました。その結果、昨年の中野区非常勤保育士「雇い止め」裁判における完全勝利からはじまり、墨田区職労における住民票等発行窓口業務直営復元への取り組み、現業職員の新規採用実現、東京自治労連として春闘期に重点的に取り組んだ偽装請負問題についての職場調査をもとにした東京労働局に対する質問書を携えての要請行動など、数多くの成果を勝ち取ってきました。
こうした職場と仕事を改善する取り組みの重要性はますます増しており、最優先重要課題として位置づけることが求められています。
2.破綻した「構造改革」路線と自公政権の終焉
2008年は1年を通して、「蟹工船」がブームとなりましたが、2008年末から2009年初にかけて一躍流行語となったのが「派遣村」という言葉でした。前者は「構造改革」路線によって貧困と格差が拡大した下で、70年も前の労働環境との相似性を想起したことに起因したものですが、後者は、この理不尽な状況を国民・労働者の連帯によって打ち破ろうとする対抗運動がはじまったものといえます。
昨年のリーマン・ショックを契機として、1980年代以降、世界中を席巻してきた「構造改革」路線のほころびとその破綻が明らかにされ、総選挙での国民の審判として、これまで10年間「構造改革」路線を推進してきた自公政権はついに終焉しました。
しかし依然として「構造改革」路線に固執し、さらなる国民いじめを画策しようとする勢力が存在することも事実です。今、私たちは「構造改革」路線と決別し、国民本位の政治を実現することができるのかどうかの大事なスタート地点に立っています。
政権党となった民主党はマニフェストなどで国民生活向上を公約の第一に掲げていますが、結成当時は自民党より先鋭な「構造改革」・改憲路線を標榜していました。民主党が政権を担うことになった下で、世論の力で新しい政治を実現させることできるのかどうかが大きく問われています。
3.アメリカ一国主義の崩壊と地球規模で始まった変化
アメリカを中心とした「新自由主義」に基づく市場原理という考え方は、急速に衰退しています。この流れは、昨年アメリカ発の「金融危機」が世界中を「恐慌」に陥れることにより、決定的となりました。そして、この影響は当初の政府・財界の予測とは異なり、日本がもっとも大きかったといわれています。その原因のひとつは、軍事だけでなく経済的にもアメリカに依拠・従属していることにあります。
昨年秋、アメリカで初めての黒人大統領のオバマ政権が誕生しました。深刻な国内経済とイラク・アフガン戦争という「ブッシュ政権の負の遺産」を引き継いだオバマ氏ですが、国内政治では2月に成立した「米国再生・再投資法」などで、大企業への課税強化、中低所得勤労者むけ減税を打ち出す一方、平和の分野では核兵器全廃を国家目標とする(プラハ宣言)など、前政権とは大きな変化を見せています。
また、イラク・アフガン戦争の見直しとともに中東諸国を歴訪するなど、関係改善を模索し、東南アジア友好協力条約(TAC)への加入など、中国、インドなどをはじめとした対アジア政策にも変化が見えています。しかしアフガニスタンへの増派など、単純に手放しで評価することはできませんが、こうした情勢の下で、日本政府のみがこれまでのアメリカの「核の傘」に固執し、地球規模で起きている大きな変化から目をそむけていることは、世界の非常識となります。
さらに「全総」に変わる「国土形成計画」などをみると、政府・財界がODA予算を投入したアジアへの進出を企図していますが、これは市場として中国、ベトナムなどのアジア諸国を考えるだけであり、真の国際貢献とは相容れるものではありません。
これまでの態度を改め、アジア諸国との関係を重視し、世界平和に貢献することこそ日本の果たすべき役割です。
4.憲法をまもる運動の発展と改憲固執勢力のゆり戻し
安倍政権における教育基本法の改悪、「改憲手続法」の制定の頃と比べると、改憲の企みは一見沈静化した様にも見えます。しかし、昨年10月には憲法とはまったく相容れない歴史観に基づく論文を発表した田母神氏を招いて、名古屋高裁判決1周年に合わせて名古屋で、さらには原水禁大会に合わせて広島で講演会を開催するなど、改憲勢力の巻き返しも激しくなっています。
一方で、私たちの運動は「九条の会」が全国で7,300を超えるなど、大きな高揚を迎えました。また、昨年4月に名古屋高裁は、「イラク派兵は憲法9条違反である」とする画期的な判決が出されました。この判決により、自衛隊は昨年末までにイラクから完全撤退せざるを得ない状況をつくり出すことができました。
いま新たに誕生した民主党中心の政権のもとで、民主党も賛成した憲法審査会がどうなっていくのか、「改憲手続法」の施行が来年に迫った現在、憲法をまもる取り組みは重要な局面を迎えています。とりわけ民主党は政権が目の前に近づくに従い、「現実政治」の名の下にこれまで一連の海外派兵法に反対してきた態度を、アメリカの意向に沿った国際支援に変えていこうとしています。また民主主義の根幹である選挙制度での比例定数80削減の狙いなど、多くの問題点をかかえた政権であることも明らかにしておくことが重要です。
5.「構造改革」路線の矛盾と、国民生活をまもる闘い
今、日本の失業者は359万人に達しています。この深刻な状況をつくり出したおおもとは労働法制の度重なる改悪によって、労働者の使い捨てが合法化されたことに因ります。
社会保障では、骨太方針による毎年2,200億円もの社会保障費削減は国民生活を直撃しました。2000年にスタートした介護保険制度は、2005年に施設の食費・居住費を自己負担とする大改悪を行いました。
保育分野では待機児問題が全国的に緊急課題となるなか、社会保障制度の砦としての公的保育を解体し、国と自治体の責任を投げ捨て、保育を「自己責任」で行うことを求める大改悪が進められようとしています。
医療の分野では、医師・看護師不足、公立病院統廃合など、「医療崩壊」といわれる状態が相次ぎました。なかでも75歳以上の高齢者を年齢のみで差別する後期高齢者医療制度に対しては、廃止を求める運動が高まりました。また、療養病床削減の本格実施や食費、居住費の自己負担化の65歳への拡大に加えて、特定健診、特定保健指導もはじまりました。
障がい者の分野では、障がいが重いほど負担が増える「応益負担」を持ち込んだ「障害者自立支援法」が2005年10月に成立しました。
年金では2000年、2004年に大改悪を行い「100年安心」のキャッチフレーズが嘘と欺瞞に満ちたものであったかが明らかになりました。
税制の面では、私たちに対して所得税・住民税の定率減税廃止をはじめとして徹底した増税を求める一方で、大企業には、法人税率の引き下げなどにより毎年のように減税を行ってきました。さらに福祉財源を口実とした消費税増税論を既定の事実のように描き出しています。しかも自民党と民主党の違いは、実施年の違いのみという構図になっています。
公衆衛生では「地域保健法」に基づく保健所の統廃合と職員削減が進んでいますが、今年の新型インフルエンザの流行とこれに伴う社会的な大混乱は、こうした政策が大きな誤りであることを事実で示しました。さらに今年の秋からさらなる大流行が予想されることから、必要な人員確保などそのための対策が求められています。
こうした「構造改革」路線に対する国民的な反対運動が後期高齢者制度だけでなく、あらゆる分野で国民諸階層から沸き起こり、その集大成が国民の自公政治NOの選択に結実したといえます。
6.矛盾が拡大する自治体「構造改革」、見直そう職場と仕事
「構造改革」路線は国民生活のあらゆる分野で私たちに痛みを押しつけてきましたが、「指定管理者制度」、「地方独立行政法人」、「PFI」、「市場化テスト」などの手法が全国の自治体を席巻しました。しかし、私たちの運動の反映もあり今日「構造改革」路線の破綻が露呈した下で、政府・財界などでも一定の見直し・再検討が議論されはじめています。
しかし、依然として「構造改革」路線にしがみつき、強権的に国民生活の危機を乗り切っていこうという勢力がまだまだ大きいことも事実です。「骨太方針2009」で国家公務員の総定数削減を、あらたに「5年間で10%以上の削減」を掲げており、地方公務員への影響とも併せて看過できない課題となっています。
こうした勢力の策動を打ち破り、職場と仕事を見直し、住民本位の自治体をつくることが今、求められています。
7.労働組合を取り巻く状況
派遣村の取り組みに関連して、「労働組合なくして今回の取り組み不可能であった」との声が村長の湯浅誠さんやマスコミからも寄せられています。
また、労働者派遣法にすら違反した「働かせ方」を正させる取り組みが、全国的に展開されています。ここでも労働基準局に対して雇用主の非を届け出、労使交渉を行う労働組合を結成し、支援していくことが大変重要となっています。
しかし、現実には労働組合の組織率・組合員数は年々低下しており、東京の自治体職場でも、職員定数削減が大きな原因となっています。都庁の知事部局の場合、2000年都区制度改革により清掃区移管が行われ、10年前に45,000人の職員が現在の定数は25,000人を割り込んでいます。また、本庁を中心に組合加入に消極的な職員が多数存在し、こうした方々の組織化が重要課題となっています。
非正規切りや最賃引上げなどの取り組みのなかで労働組合をつくり、組織の飛躍が勝ち取られるという事例が全労連大会で明らかになっています。「闘ってこそ前進できる」の確信が共感を呼んでいます。
同時に、「官製ワーキングプア」と称される労働者が自治体のなかに急速に増加し、東京都内の自治体では25~30%が非正規労働者となっている実態があり、三多摩では50%を超える自治体も存在しています。自治労連は組織化に力を入れていますが、まだまだ広大な空白が存在し、この取り組みも急務となっています。
8.「地方分権」、道州制をめぐる情勢
道州制は「国のかたち」を変えるという国家の改造計画にその狙いがあり、2004年に第28次地方制度調査会が「道州制のあり方に関する答申」を行ったことなどで具体的な議論となりました。道州制論議が財界のリーダーシップの下に強力に進められていることをみれば明らかなように、多国籍企業との激しい企業間競争に打ち勝とうとする財界の戦略があることも事実です。
そして、このことと軌を一にしているのが「地方分権」改革です。実はこの動きも「構造改革」路線の一つですが、一部知事の主張などにみられるように、「地方分権」を叫べば「善」といった風潮があることも事実です。昨年12月の「地方分権推進委員会」の第二次勧告では、義務付け・枠付けについての考え方が出されましたが、これは基本的に国の責任放棄を合法化しようとするものです。
東京都区もこうした動きに併せて、都区制度についての検討を現在精力的に行っており、三多摩を含めて、道州制・地方分権の課題は、今後の取り組みが重要となっています。
また、この「国のかたち」を変えると企まれている一連の策動の一つに「公務員制度改革」があります。今年春には「工程表」が決定され、当初計画を2年間前倒しして、2010年中の国会提出をめざしています。この問題では、奪われた「労働基本権」を全面的に取り戻すことが重要な課題ですが、同時に「戦争できる国」を担う公務員という政府・財界の目標が大きく横たわっています。
9.石原都政をはじめとした都内自治体の動向
1999年に誕生した石原都政もちょうど10年を迎えました。小泉「構造改革」に先だってはじまった都政版「構造改革」により、高齢者福祉の予算は当時の全国2位から最低の47番目まで落ち込みました。また、都立病院では16あった都立病院の半減計画を進め、「地方独立行政法人化」、「PFIによる建て替え」が横行しています。
また第3期石原都政では「10年後の東京」に基づいた無駄使い・悪政が続いています。
第一に、2016年東京オリンピック招致を都政のあらゆる分野で振りかざし、招致費として表に出ている150億円をはるかに超える無駄使いを行っています。さらにオリンピックを口実に、三環状道路など大型幹線道路建設を強硬に推し進めています。
第二に、破綻した新銀行東京問題です。2003年都知事選挙時の公約ですが、当初の1000億円どころか、昨年追加出資した400億円も含めて、都民の貴重な血税がどぶに捨てられたといっても過言ではない状況です。都議や国会議員までも加わっての口利きや、不正融資により行員が逮捕されるなど、社会的信用も完全に失墜しました。こうした事態を受けて金融庁は東京都に対して、改善計画書の提出を求めましたが、東京都は、都の責任を認めず、旧経営陣に責任を押しつけるという態度に終始しています。また、この不況の中で最も期待されているはずの「貸し渋り」、「貸しはがし」対策についての言及もありません。
第三に、築地にある中央卸売市場の豊洲への移転問題です。築地という都心の一等地を「都市再生」のための格好の場所として狙っている石原知事は、有害物質が大量に検出された豊洲移転に固執し、有害物資除去費に当局発表だけでも600億円の膨大な都民の税金を投入しようとしています。
また「財政再建推進計画」に基づく職員定数削減攻撃と都政版「構造改革」は都民生活にも重大な支障をきたすとこととなりました。特に保育分野では、待機児童問題が焦眉の課題となる一方、施設や配置基準に問題のある認証保育所を全国で初めて石原都政が認めたことは重大です。実際、様々な問題が発生している認証保育所ですが、今国が進めている公的保育制度解体攻撃の手本になっている事実は看過できない問題です。
都内の区及び市町村では、基本的に石原都政と同様な、開発型の行財政運営を強行しています。しかし、財政的な逼迫状況が進んでいる下で、都が十分な財政保障を行わずに事務事業を移管・移譲したり、「リストラ」の達成度に基づき、多摩の市町村に対する交付金額の決定に対して反発する自治体も出ており、こうした矛盾にも目をむけて、共同の闘いを重視して取り組むことが求められています。
こうした情勢の下、7月12日投票で都議会議員選挙が行われました。その結果、自民・公明が過半数割れとなる一方、民主党も過半数には届かないという議会勢力となりました。石原都知事自身も今後の都政運営の難しさを公言しています。
しかし、都民要求の前進という目で見た場合、この状況はチャンスでもあります。共同の運動をいっそう発展させ、都民本位の都政実現にむけて会派要請をはじめとした取り組みを旺盛に展開することが求められています。
Ⅲ.運動の基調と重点課題
東京自治労連は職場組合員の要求実現と住民生活の向上をめざし、すべての自治体・公務公共労働者を視野に入れた運動の発展と組織強化と未組織の組織化を進めます。
都民の暮らし・福祉を守るため、来るべき2011年の都知事選挙を展望するとともに、東京自治労連結成20周年にむけて諸闘争を大きく前進させ、以下の運動の基調と重点課題に基づいて一年間の運動を進めます。
1.憲法をくらしと職場にいかし、地域住民の安全・安心と福祉の向上、生きがい働きがいのある元気な職場づくりを進めます。すべての自治体・公務公共関係労働者の賃金・くらしと労働条件・権利を守り、自治体「構造改革」路線をはね返すために闘います。自治体ワーキングプア根絶を掲げ、全労連が提起した「安定した良質な雇用を求める運動(雇用闘争)」を自治労連・東京地評に結集して取り組みます。
憲法9条改悪を許さず、核兵器廃絶への流れを大きくしながら平和と民主主義をまもる闘いを前進させます。憲法9条をまもれの世論と運動をいっそう職場・地域に広げて「組合員1人10筆署名」の達成にむけて取り組みます。核兵器廃絶にむけた国際情勢の進展をふまえて、節をもうけた「核兵器のない世界を」署名の取り組みやNPT再検討会議要請団派遣など核兵器廃絶の運動を前進させます。
日米軍事同盟追随、大企業本位の国政を国民本位にあらため、「構造改革」路線の転換と組合員・国民の要求を前進させるために、政党支持の自由・政治活動の保障の原則を堅持して政治啓発活動を行います。また、2011年4月の都知事選挙で私たちと都民要求を前進させる都政の実現にむけて、要求と政策、体制の確立等の準備を進めます。
2.国民本位の税・社会保障制度の実現や地球環境をまもるため、大企業に社会的責任を果たさせ、貧困と格差をなくし、人間らしい労働と生活の確立など国民的要求実現にむけて闘います。
地域住民団体等と共同して、道州制導入・「地方分権」改革や自治体「構造改革」路線による公的責任放棄を許さず、公共性・専門性・継続性・安定性の確保・拡大に全力を挙げます。地域住民に責任を果たせる自治体業務の執行体制を確保し、職場要求に応える予算・人員要求闘争を進めます。同時に、新たに成立した「公共サービス基本法」の具体化を自治体当局に求めるとともに、公契約運動を地域労組とともに取り組みます。
また、都内各団体との共同を広げながら、東京自治研集会の成功にむけて取り組みます。
公的保育制度の改悪を許さず、医療制度の改善と医療従事者確保・地域医療の充実など社会保障制度を拡充させます。その財源として消費税の増税を許さず、能力に応じた負担の適正化と税金の使い方を国民本位へと転換させます。
3.職場要求に基づく全組合員参加の運動を基本に、すべての闘いを自治体・公務公共関係労働者の組合員拡大、「次世代育成」をはじめとした組織の強化につなげ、結成20周年に向けて5万人東京自治労連建設を大きく前進させます。
職場要求実現の闘いと組織の拡大・強化を常に車の両輪として、本部と単組が一体となって取り組みます。全国的全都的に成功させてきたおきなわプロジェクトの成果を「次世代育成」につなげます。また、組織拡大の重要な一翼を担う自治労連共済の前進をはかります。
Ⅳ.具体的な課題と取り組み
1.憲法改悪に反対し、平和と民主主義をまもる闘い
1.憲法改悪反対の運動
1)東京自治労連が進めている憲法署名は、改憲を狙う「国民投票法」が施行される2010年5月をひとつの節として、目標の「組合員1人10筆」に到達するため、引き続き「憲法署名欄付ハガキ」等の活用を進めます。
2)「憲法改悪に反対する東京共同センター」の提起する「9の日宣伝」をはじめとした諸行動に積極的に参加します。
3)「憲法をいかす自治体労働者東京連絡会」は、11月30日に第5回総会を開催します。
総会では、「会」への加盟団体の拡大をはかり、「国民投票法」の公務員の権利制限問題など学習や交流を深め、憲法改悪阻止の運動の飛躍を勝ち取る機会とします。
4)地域の「九条の会」や、地域の共同センターの取り組みを各単組で強めます。
5)自治労連の第5回憲法闘争交流集会(11月7日)に積極的に参加します。
2.核兵器廃止、基地再編強化反対など平和をまもる運動
1) 2010年5月のNPT再検討会議の成功にむけ、「核兵器のない世界を」の署名(目標・組合員一人10筆)を軸に、職場・地域から核兵器廃絶の世論を盛り上げます。
2)名古屋高裁「イラク派兵違憲」判決を生かし、自衛隊のインド洋での給油活動の停止と「自衛隊海外派兵恒久法」に反対します。
3)日本原水協が進める3・1ビキニデーや原水爆禁止2010年世界大会に取り組みます。
4)「非核日本宣言」などの自治体賛同を広げるための運動を地域の平和団体などと一緒に進めます。
5)横須賀へ原子力空母の配備がされるなど在日米軍基地の再編強化が進められているなか、再編強化に反対し、横田基地をはじめとする在日米軍基地撤去に向けた取り組みを強めます。
6)横浜で開催される「2009年日本平和大会」(12月11~13日)の成功にむけて積極的に参加します。
7)国民保護法や防災訓練の名による米軍・自衛隊参加の市民訓練に反対します。
8)平和記念館の設立運動や「非核の日本を求める東京の会」の運動を進めます。
9)外務省の「核密約」問題について、真相解明を求めます。
3.表現の自由などの民主主義をまもる闘いや争議団勝利への取り組み
1)ビラまき弾圧事件(世田谷、堀越、葛飾)裁判を支援します。
2)日の丸・君が代を強制させない運動を強めます。
3)警察主導による地域における監視カメラの設置など民主主義を犯す国民監視活動
を許さない闘いを強めます。
4)国鉄労働者の解雇・不採用、社会保険庁解体・分限免職など、国による不当な攻撃を許さず、各種争議の勝利をめざし支援します。
5)衆議院比例代表削減は、民主主義の根幹に関わる選挙制度の改悪として反対します。
2.生活向上・労働時間短縮・「働くルール」確立をめざす取り組み
1.すべての労働者が生活改善につながる大幅賃上げをめざして
1) すべての労働者の大幅賃上げ
(1)すべての労働者の生活改善につながる大幅賃上げに取り組みます。
(2)大企業の社会的責任を追及し、内部留保を企業内外労働者の賃上げ・雇用確保などに回させる運動を強めます。
(2)国に対して外需頼みではなく、内需拡大を進める政策転換を求めるとともに自治体に対して、中小企業の支援などの政策を充実するように働きかけます。
2) 最賃の大幅引き上げ
(1)生活保護基準との整合性を確保した最低賃金額を要求に掲げ、東京地評の闘いに結集するとともに、地域からの取り組みを重視し早期実現へむけて全力で取り組みます。
(2)全国一律最低賃金制度確立にむけて、自治労連・東京地評とともに闘って行きます。
3) 公契約条例の制定、公正な生活保障賃金の実現をめざして
(1)日本政府のILO94号条約批准や「公契約法」制定・国内法の整備へむけて、地方議会や自治体に対する働きかけを強めます。特に、自治体キャラバンにおける重点課題に位置づけ、全単組の参加で取り組みます。
(2)自治労連の「公契約モデル条例案」を活用し、職場世論の結集を図り、地域との共同を進めて、公契約条例制定へむけて取り組ます。
東京段階では、引き続き東京土建等との定期協議の課題に位置づけ、各自治体に向けた要求と運動の具体化を図ります。
(3)男女共同参画、障がい者雇用、環境や人権など価格だけでなく、公共サービスにふさわしい「質」を担保する「政策入札」の実現を追求します。
4)雇用の確保・働くルールの確立をめざす闘い
(1)労働者派遣法の抜本改正、違法派遣等の根絶、有期雇用の規制強化をめざし、全労連の「雇用闘争」(安定した良質の雇用を求める闘い)を強めます。
(2)雇用保険の抜本改正、職業訓練充実・強化をはかり、失業時の生活保障を整備する闘いを強めます。
(3)調理職・用務職など現業職場を中心とした「職場から偽装請負・違法派遣の一掃へ向けて」(6月24日付け)闘争方針に基づいた取り組みを強化します。
(4)労働時間の短縮、超過勤務規制など働くルールの確立、労働法制改悪の問題を自治労連・東京地評に結集して取り組みます。
5) 2010国民春闘勝利へ向けて
国民春闘勝利へ向けて、別途、「2010国民春闘方針」を確立して闘います。
2 公務員賃金の大幅な引き上げをめざして
(1) 賃金確定闘争では、交渉組織である都労連・特区連の闘争に主体的に結集して闘うとともに、三多摩協議会を軸に、各自治体の闘いの情報交換と支援など、運動の前進へむけて必要な取り組みを進めます。
(2)人事院勧告・人事委員会勧告時期の闘い、賃金確定闘争を通じて官民一体の闘いとして、自治労連・東京地評に結集し、職場と地域からの闘争を推進します。
(3)地域手当の国並み引き下げ攻撃に対して、構造的な地域手当の矛盾や人材確保への悪影響などを主張し、改善を求めて取り組みます。とりわけ三多摩地域の地域手当問題などについては、具体的な対応を進めます。
(4)国家公務員の住居手当の「持ち家」部分廃止は、自治体にも大きな影響を及ぼします。国と自治体の違いを明確にし、廃止の不当性や民間の支給状況との乖離を明らかにし、住居手当廃止反対、住居手当の拡充を掲げて闘います。
3 現業賃金をまもる闘い
1)現業・非現業一体で現業賃金水準改悪を許さない闘いを進めます。特に、「民間準拠」を口実とした現業賃金引き下げ攻撃は、現業職場そのものを廃止する狙いを持つものであり、賃金闘争と自治体現業職場の意義と役割を結びつけて共同の闘いとします。
2)特別区の技能・業務系の職員の多くは、昇任しても給与処遇に反映されないなど「制度矛盾」に陥っており、昇任制度や給与制度の改善要求実現へむけて各区職労とともに取り組みます。
3)総務省「技能労務職員の給与に関する基本的考え方に関する研究会」の動きは、現業職員の給与決定方法にまで検討が及んでおり、自治労連に結集して、労使自治に対する不当な介入を許さない闘いを進めます。
4 能力・成果主義人事給与制度との闘い
1)「能力・成果主義人事給与制度」は、労働条件改悪とともに公務労働を破壊するものにほかなりません。制度導入の有無に関わらず、制度の問題点を系統的に明らかにし、職場世論形成を重視し闘います。
2)制度の有する重大な問題点を踏まえて、未導入単組においては制度導入の阻止、人事評価制度の賃金リンク阻止を掲げ、徹底した労使協議・労使合意を貫いて闘います。
3)都区をはじめとして、評価結果に基づく昇給決定などが実施された単組においては、検証を進め、問題点を明らかにして、制度改善の取り組みを行います。
4)目標管理制度・人事評価制度については、公務公共関係職場における実態を踏まえて民主的人事制度の確立を対置して闘います。
5 自治体に働く非正規・公務公共関係労働者の労働条件改善の闘い
1)直接雇用臨時・非常勤職員の大幅賃上げなど労働諸条件改善を求める闘い
(1)人事院「非常勤職員に対する給与指針」や正規労働者との均衡の取れた待遇確保を目的とする改正パート労働法を積極的に活用し、直接雇用臨時・非常勤職員の賃金・労働条件の抜本的な改善をめざして、正規・非正規一体の闘いを進めます。
(2)雇用の安定、労働条件改善のために、自治体の正規職員化をめざす取り組みを強めます。
(3)直接雇用非常勤職員に対する不当な雇い止め(雇用年限設定)問題は、非常勤職員の最大の課題です。都内自治体で、実施されている雇用更新回数限度については、総務省通知や国会質疑などにおいても否定されていることを踏まえ、その撤廃へむけた運動を進めます。都当局の5年有期雇用化問題での公務公共一般の都労委闘争を支援します。
(4)直接雇用臨時・非常勤職員の抜本的な労働諸条件改善を実現するには、法制度の改善・整備が求められています。自治労連が提起する「任期の定めのない、均等待遇に基づく短時間公務員制度」確立に向けた職場討議を進めます。
2)公務公共関係労働者の労働条件改善をめざす闘い
(1)自治体業務に従事する公務公共関係労働者の労働諸条件を抜本的に改善する闘いを進めます。
(2)公共サービスの質を確保するために、委託費、指定管理者制度における協定書、請負契約における仕様書などについての検証を進め、公契約の視点で、その具体的改善へむけた取り組みを進めます。
3)介護関係職員や消費生活相談員の労働条件の引き上げ
(1)介護関係職員の処遇改善については、2009年度補正予算に盛り込まれた「介護職員処遇改善交付金」(平均1万5千円の給与引き上げ)を事業者に確実に活用させて、すべての介護関係労働者の処遇改善をかちとります。
(2)消費生活相談員の処遇改善は、組合員の大きな運動により、引き上げることが出来ました。補正予算などにより財政措置がされているので、当局にその実行を迫ります。
6 安心して働き続けられる自治体関係職場をめざして
1)長時間・過重労働、「不払い残業」をなくす闘い
(1)過重労働から健康をまもる闘いと単組での人員予算要求闘争を結合し、運動を進めます。単組間の交流を深めてお互いの運動の前進を図ります。
(2)恒常的な超過勤務の解消を求め、超勤手当不払をなくすとともに、2009人事院勧告ふれられた超過勤務手当の割り増し、職員の希望による代替休制度などを実施させます。
(3)36協定締結問題では、長時間労働と不払残業の解消に結びつく実効ある36協定締結を重視して対応を進めます。
(4)坂本通子さん(自治労連都庁職教育庁支部)「不払超過勤務手当請求裁判」の支援に取り組みます。
(5)当局責任による長時間労働の実態調査、啓発活動、「ノー残業デー」などの実施を求める運動を重視します。
2)すべての職場での所定内労働時間短縮をめざす闘い
(1)2008人事院勧告で示された1日8時間を7時間45分に短縮する労働時間短縮が未実施の都などでの時間短縮を進め実現を図ります。人事院規則で制度化された変則勤務における休息時間の取り扱いなどを重視して取り組みを進めます。
(2)育休制度改正および、人事院勧告で新設された「短期介護休暇」および「子の看護休暇」拡充についても確実に実施させるよう取り組みを強めます。
(3)総労働時間短縮へむけて、各種休暇制度の拡充、年次有給休暇取得率向上など、職場の権利点検を強め、人員要求闘争と結合して取り組みます。
3)労働安全衛生活動を強化する取り組み
(1)労働組合としての労働安全衛生活動の強化を基本に、非正規労働者も含めた安全委員会・衛生委員会の体制確立を図り、すべての職員が安全で安心して働ける職場づくりをめざします。
(2) 第9回東京自治労連労働安全衛生活動交流集会(2010年9月)を開催し、単組での運動の前進を図ります。
(3)メンタルヘルス対策の改善を図るため、自治労連討議資料「メンタルヘルス対策を推進するための自治労連の要求と方針(案)」の学習会など学習活動を強化し、モデル要求を活用し要求提出とその実現をめざします。
(4)厚労省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(基発第0331001号)にもとづき、当局に「心の健康づくり計画」、職場復帰プログラムの策定を要求します。策定済みの単組では、取り組みを検証し、実効あるものに改善させる先進的取り組みをめざします。
(5)メンタルヘルス不調のひとつの要因である、セクハラ・パワハラについて、自治労連の2009年夏季のアンケート結果を活用して対策強化を求めます。
(6)自治労連の開催する「メンタルヘルス・労働安全衛生活動交流集会」などに積極的に参加し、単組での活動を強化します。
(7)健康診断の内容充実、特殊健康診断の実施、非正規職員などすべての職員の健康診断制度の確立を重視します。
(8)公務災害認定に関わって、不服審査の中央への一段階化に反対し、「地方公務員災害補償法(不服審査制度)改正案」、「労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律案」の廃案を求め、闘いを進めます。
7 仕事と生活の両立支援制度の拡充など働き続けられる職場をつくる取り組み
1)男女雇用機会均等法をいかし、昇任・昇格をはじめ、あらゆる直接・間接差別の撤廃、相談・問題解決機関の設置などにより、セクハラ・パワハラの根絶、ポジティブアクション(積極的な男女平等促進)を推進して、民主的で安心して働き続けられる職場づくりを進めます。
2)3年の中間見直しにあたる「特定事業主行動計画」に対して、単組としての検証や要求反映の取り組みを進めます。
3)母性保護や男女ともに健康で働き続けるために、2009人事院勧告による①配偶者が育児休業している職員の育児休業の取得②配偶者が育児休業している職員の育児短時間勤務・育児時間の取得③育児を行う職員の超過勤務の免除④介護のための短期の休暇制度⑤子の看護休暇の期間の拡充、の実施を求めて取り組みます。
4)様々な権利が行使できるように制度改善、職場づくりに取り組みます。
8 公務員制度改悪に反対し、労働基本権の全面回復をめざす闘い
1)公務員制度改革に対する闘い
(1)憲法15条の「全体の奉仕者」を否定する公務員制度改革の攻撃に対して、ILO勧告に基づく「労働基本権回復」・「民主的公務員制度」確立をめざして、職場の世論形成を重視し、職場からの闘いを進めます。
(2)労働協約締結権の回復の議論が進んでいます。争議権を含めた労働基本権完全回復の取り組みを、全労連・公務労組連に結集して進めます。
(3)労働協約権の回復後には、「要求提出、交渉、妥結」という運動が定着できるように準備を進めます。
2) 定年延長の取り組み
2009人事院勧告で雇用と年金支給開始年齢を連動させるために、定年延長が検討されています。給与制度改悪を含めて制度設計が組み立てられようとしています。給与制度と切り離して検討するなど改善要求を明確にして闘いを進めます。
3)危機管理を口実とした反動的な職員研修の実施、懲戒処分指針の一方的な変更、労働組合に対する不当な介入・干渉など、権利侵害に対して、東京自治労連弁護団と連携をとりながら闘いを進めます。
9.公務員共済制度、福利厚生の拡充を
1) 共済制度
自治労連の共済健保議員団方針に基づき、以下のとおり、取り組みます。
(1)被用者年金一元化の問題については、これまでの職域年金部分に代わる3階部分の制度構築、共済組合としての運営継続などの課題で対政府要求行動を進めます。
(2)高齢者医療制度、特定健診・保健指導の導入による短期財政悪化などについて実態把握や政府・関係機関への要請を取り組みます。
(3)共済・健保議員団活動の活性化のために、ニュースの発行を目指します。
(4)議員選挙に積極的に取り組むとともに、到達点を踏まえ、各単位共済の理事、議員と連携をとりながら、要求実現に向けて奮闘します。
2) 福利厚生
福利厚生事業の廃止・縮小が全国的に広がっています。その理由は財源がすべて税金であるという理由からですが、そもそも地方公共団体が「職員の保健・元気回復その他福利厚生に関する事項」について、計画・実施することは地方公務員法に自治体の義務として定められているものです。民間の動向なども踏まえつつ、住民に理解される制度として、その充実に努めていきます。
3) 労働金庫
(1)関係者会議などを設定し、要望・要求を把握します。
(2)全国合併に向けた取り組みについては、組合員に対して状況を伝えるとともに、必要な意見反映を行います。
4) 全労済
(1)都本部の動向を単組・支部に伝えます。
(2)自治労共済との統合問題については、その都度状況を知らせとともに必要な意見反映を行っていきます。
3.国民犠牲の大増税を許さず、社会保障の充実をめざす闘い
1)国民生活を脅かす課税強化や消費税増税に反対し、税制の抜本的改正を進める闘い
①「消費税廃止東京各界連絡会」に引き続き参加し、消費税増税反対の運動を共同して行います。消費税は、低所得者により重くなる逆進性をもつため、食料品を始めとする生活必需品への消費税課税をやめることと、「財源は、大企業・高額所得者に対する応分の負担」の原則を掲げて政府・自治体への要請を行います。
②所得税、消費税を含む税制度についての学習を強め、国際的に見て低い「所得再分配効果」を高めることを求めます。
2)「骨太方針」に基づく社会保障費2,200億円削減方針を撤回させ、医療、介護、年金など社会保障を拡充する取り組み
本来、貧困をなくし生活を支えるはずの社会保障制度が、逆に日本では医療、介護、国保、生保、障害者福祉、保育などの諸制度が機能せず、生存権そのものが脅かされる状況になっています。「構造改革」路線をストップさせ、社会保障削減路線の抜本的転換を図るために、住民共闘を重視した運動を構築します。
(1)後期高齢者医療制度廃止の取り組み
国会闘争では制度の廃止を求める取り組みを進め、同時に、制度の問題点に対する改善要求闘争を取り組みます。
①「後期高齢者医療制度の廃止を求める東京連絡会」に結集し、制度の廃止を求めるとともに、75歳以上の医療費の無料化を求めて運動を進めます。
②都・区市町村に対して、保険料引き下げと負担軽減のための財政措置を求めます。
③広域連合に対して、保険料減免をはじめ制度改善を行うよう要請を行います。
④当該職場の要求実現と、労働条件確保に向けた取り組みます
(2)国民健康保険制度の改善・充実をめざす取り組み
①国保料・税の引き上げと保険証取り上げに反対し、東京社保協や住民団体とともに国や自治体に対して国保料・税の引き下げと国庫負担の増額の運動を進めます。
②減免制度の拡充など、制度改善にむけ運動します。
③国保料・税の徴収職場の民間委託について問題点を明らかにし、委託を許さない闘いを進めます。
(3)だれもが安心できる医療制度拡充を求める取り組み
①自治労連の「いのちと地域を守る大運動」を具体化し、「地域医療計画」などに対して、医療部会とともに問題点を学習し要求を確立し、自治体当局などに要請を行います。
②安全・安心の医療・看護を実現するため医師・看護師の大幅な増員を求めます。自治労連が作成したリーフ「看護師の二交代・長時間夜勤を考える」を積極的に活用し、医療職場の過酷な実態を改善し、働き続けられる勤務体制を求める運動に取り組みます。
(4)安心できる年金制度の構築をめざして
①全額国庫負担による「最低保障年金」制度確立にむけた運動を進めます。また、年金財源に対する事業主負担の強化にむけて取り組みます。
②安心できる年金制度の確立を求める署名と、学習・宣伝行動に取り組みます。
③社会保険庁解体による諸問題への無責任な対応を許さない闘いを進めます。
(5)生活保護制度改悪に反対し、だれもが安心して受けられる制度確立のために
①生活保護制度の改悪に反対し、関係団体と共同した取り組みを進めます。
②生活保護職場における運用の問題点を明らかにし、社会福祉部会とともに職場要求と制度改善の取り組みを進めます。
③ケースワーカーの配置基準(80対1)に基づく人員配置を実現させるため、増員要求の取り組みを強化するとともに、配置基準そのものの改善を求めて運動します。
④「生存権権裁判を支える東京連絡会」に参加し、老齢加算・母子加算の復活を求めて取り組みを進めます。
(6)介護制度・介護労働者の改善にむけた運動
介護労働者の離職率増加によるサービス不足が深刻化するなど介護制度の崩壊が社会的な問題となっている状況のなか、利用者・事業者と共闘し、国民的運動を進めます。
①国・都・区市町村の負担を大幅に増やし、保険料や利用料の引き下げ、特養ホームの増設等介護サービスの拡充を求めます。
②2010年の介護制度見直しに向け学習を進め、公務公共サービスの向上を図るため、介護保険制度の抜本的改善を求めます。
③「介護をよくする東京の会」に結集し、2009年4月に実施された介護認定方式の変更によるサービスの抑制を見直し、必要な介護を受けられる制度にすることを求めます。
(7)障がい者福祉制度の改善を求める取り組み
①障がい者自立支援法の応益負担の廃止、報酬引き上げ、日割り単価の廃止など抜本的見直しを求めるため、関係団体と共同し闘いを進めます。
②「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす・東京の会」を積極的に支援します。
③公立障がい者福祉施設の民営化に反対します。
(8)公的保育制度、学童保育、児童館を守り充実させる取り組み
①2011年中の通常国会に公的保育制度解体の法案が提出されようとしています。それにむけて制度設計がなされており、解体を阻止するために、「保育・学童保育闘争委員会」を中心とした闘いに取り組みます。
②保育の実施は、認可保育所での保育を基本とし、深刻化している待機児問題を解消するために、認可保育所の新増設を求め、取り組みます。
③認定こども園については、その問題点を踏まえて、新設反対と既設園の改善へむけて取り組みます。
④公的保育制度の解体を狙う都独自の認証保育所制度の問題点を明らかにし、抜本的改善を求めます。
⑤保育・子育て支援の予算増額、職員配置基準の改善を求めるため、署名や自治体に対し要請等を行います。
⑥学童保育事業を全児童対策事業に吸収・解消させる動きに反対し、両事業の充実・改善に向けた運動を取り組みます。
⑦住民本位の地域の保育・子育て支援政策づくりに取り組んでいる単組を支援するとともに、情報交換を行い、その運動が広がるように取り組みます。
⑧保育園・児童館の民営化・委託化、調理・用務の民間委託を許さず、利用者が安心して利用できる施設をめざします。
(9)公衆衛生の充実にむけた取り組み
①公衆衛生に対する自治体の公的責任を明確にさせ、特定検診・特定保健指導の医療保険者義務化に伴うサービスの低下をまねかないよう、自治体に対して公衆衛生の体制・機能の強化を求め、公衆衛生部会、関係単組とともに職場・地域からの運動を進めます。
②高齢者虐待、児童虐待、精神疾患者の増大等から保健所機能の強化が求められています。保健所の増設、体制強化と保健師等の関係職員の大幅増員を求めます。
③新型インフルエンザに対しては、医療従事者の確保などの体制整備と労働条件の改善を求めます。
3)くらし・教育・環境問題などの取り組み
(1)中小企業の営業・農業など産業をまもる取り組み
①地域・地場産業の育成支援や中小零細業者支援に向け、制度融資など拡充に向け諸団体と共同し取り組みを強化します。
②食の安全を確保するため、食料自給率向上など食料主権確立の立場から、東京の農業をまもる取り組みを進めます。そのためにも、給食への地産地消の拡大を進めます。
③日本の農業、特に主食である米作に壊滅的打撃を与える日米の自由貿易協定(FTA)締結に反対します。
(2)教育の取り組み
①「子どもと教育を守る東京連絡会」に参加し、小学校・中学校における少人数学級の実現、給食費の無料化などの運動を進めます。
②過去の日本の侵略行為を否認し、美化する教科書を採択させない運動を広げます。
③高校・大学・大学院・専門学校等について、返済不要の奨学金制度を求めます。
(3)子どもの貧困についての取り組み
①「貧困の連鎖」から子どもをまもるため、社保協など関係団体と連携して、貧困問題の解決のために取り組みます。
②保護者の失業・倒産などによる経済的困窮に対する高校生の就学支援の創設を都や区市町村に求めていくとともに、高校教育の無償化に向けて運動を強めます。
③「子どもを貧困と格差から救う連絡会議」に参加し、子どもたちの貧困問題に関わる情報交換や学習活動に努めます。
(4)環境問題の取り組み
地球温暖化や環境問題は人類的課題となっており、自治労連の方針に基づき、各単組で取り組みを進めます。
①各自治体における温暖化防止の取り組みとして、温暖化防止計画の立案や目標設定などの施策を具体化させる交渉を進めます。
②地球温暖化防止や環境問題の取り組みとして、省エネ・廃棄物削減などを職場から進めます。
③CO2の排出を拡大するような高速道路の無料化や、1メートル1億円もの建設費がかかる環状道路の建設などに反対し、運動を広げます。
4.自治体「構造改革」に反対し、地方自治をまもり発展させる闘い
1)自治体「構造改革」を許さず住民本位の改革をめざす取り組み
(1)「集中改革プラン」、行革推進法による一方的な職員削減・非正規化・民間委託化を許さず住民の暮らしと権利をまもる自治体をつくる取り組み
①住民サービスに必要な職員の増員を求め、民営化・民間委託、事業廃止・縮少を許さない取り組みを強めます。
②現業問題については、別途方針を確立し、重点課題として取り組みます。
③福祉施設や社会教育施設などの民間委託に反対し、職場を基礎に、施設利用者や住民との共闘で住民要求を実現する闘いを進めます。
④指定管理制度・市場化テスト・地方独立行政法人・PFIなどのアウトソーシングの実態を検証し、住民サービスの低下等の問題点を明らかにし、直営化を求めます。
⑤民間委託や非正規化された職場・職域について、組織拡大も視野に入れ、課題の整理・解決を行うよう運動を進めます。
⑥憲法をいかし、住民福祉を増進する自治体の責務を踏まえた行政を実現するために、職場と地域から人員予算闘争を推進します。
⑦住民犠牲の「行革」を推進する三多摩地域の自治体への東京都「市町村総合交付金」の経営努力割廃止を強く求めます。
(2)自治体における偽装請負・違法派遣などを解消するための取り組み
①自治体における偽装請負・違法派遣などを解消するため、自治労連が作成した「公務公共サービスの基本は直接雇用です」パンフレットも活用し、取り組みを強め、既に委託化されている業務の検証を進めます。
②住民生活を守る第一線の現業職場については、公務公共性を拡大させる積極的な取り組みを進め、偽装請負・違法派遣をなくし、直営の堅持・拡充・職域の確保を求めます。
③市区町村窓口業務の民間委託問題は、直営化を実現した墨田区職労の到達点を広め、正規職員の採用、労働条件の改善を求め、新たな委託導入を阻止します。
(3)地方分権・都区制度改革に関する取り組み
①地方分権改革推進委員会第2次勧告についての検討・研究を行い、住民サービスの低下を招かないよう、運動を進めるとともに、第3次勧告等に対して地方自治法の改悪を許さない立場から必要な対応を取ります。
②都区制度改革問題について、「都区のあり方検討委員会」の検討状況を研究し、住民自治をまもる立場から自治体行財政委員会などで調査分析を深めます。
③「道州制」について、政府財界の狙いと問題点を明確にし、住民自治を拡充する立場から、要求と政策を明らかにして運動を進めます。
(4)指定管理者制度と闘い、「公の施設」の公共性をまもり、利用者と施設労働者の要求実現をめざす取り組み
①指定管理者制度は、公平性、専門性、継続性、安定性などの面から多くの問題点があり、制度の廃止・直営化をめざして取り組みます。
②文部科学省が、公共図書館と博物館を対象に指定管理者制度の実態調査・研究を行い、 2009年度内に結果報告を行うとしています。その結果を待たずには、新たな指定管理者制度の導入を行わないよう各自治体に求めます。
(5)市場化テストを拡大させない取り組み
①市場化テスト法に基づく「特定公共サービス」の拡大など、自治体業務における市場化テスト拡大を許さない取り組みを自治労連とともに進めます。
②「民間事業者による提案」、「官民競争入札」など市場化テスト的な手法を用いた自治体業務の民間丸投げを許さない取り組みを行います。
(6)地方独立行政法人、PFIなどに対する取り組み
①地方独立行政法人化で、公務・公共性の変質と労働条件の一方的改悪が行われていることを踏まえ、地方独立行政法人化に反対するとともに、その公務・公共性の拡充と労働条件の改悪を許さない闘いを進めます。
②府中病院、駒込病院などで導入されたPFIについて問題点を明らかにし、自治労連が作成した「PFIパンフレット」も活用し、住民と共同した取り組みを行います。
(7)電子自治体と監視社会に対する闘い
自治体は多くの住民固有情報を保有しており、電子化された情報は容易に寄せることができます。それが住基ネットと結びつくことによって、一気に国家による国民監視社会をもたらすこととなります。
①住民の安心・安全を保つ立場から、住民情報に関わる業務の民間委託化に反対し運動を進めます。
②個人情報の流出などの危険があり、個人にも、自治体にも情報がコントロールできないという問題を抱えている住基ネットへの接続について、総務省による国立市への不当な干渉を許さない運動を広げます。
③2011年の導入に向けて検討されている「社会保障カード」(仮称)については、国民のプライバシー保護の観点から重大な問題点が指摘されています(2007年12月13日付、日本弁護士連合会の意見書)。「国民総番号制」につながる導入に反対して闘います。
(8)地域医療と自治体病院をまもる闘い
政府・財界は、自治体構造改革の一環として「公立病院改革ガイドライン」を示し、その中で、「経営効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し」を強要しています。医療崩壊と呼ばれる現状を改善するため、「安心してかかれる公立病院」を求めて、統廃合・民営化を止めさせ、地域医療の充実を求めます。
①経営効率優先の都立病院の再編に反対し、都立3小児病院の廃止をはじめとした公立病院つぶしの攻撃に対して、当該単組、医療部会、関係団体とともに、個人署名・団体署名・都民宣伝などを軸に共同を拡大し、地域世論結集を強め、対都行動を展開します。
②町田市民病院をはじめとする公立病院の充実に向け、当該単組等と連携し、地域住民との共同の運動を進めます。
③公立病院をまもる闘いを医師・看護師の労働条件改善と大幅増員運動と結合し、積極的に取り組みます。
④「東京医療関連労働組合協議会」に引き続き参加し、ともに運動を進めます。
2)地方自治研究集会の成果を踏まえ、自治研活動を推進する取り組み
(1)「構造改革」が奪った「住民のために良い仕事がしたい」という願いと誇りを取り戻し、仕事と職場に憲法をいかし、住民の暮らしと憲法をまもる職場と自治体をつくります。だれもが安心して暮らせる地域をつくるために、職場自治研究活動を推進し、住民との共同で地域自治研運動を進めます。自治労連が提案する「憲法がいきる、こんな地域と日本をつくりたい」を職場、地域で深め広げます。
(2)自治労連が提起してい「対話と提言」の運動を積極的に受け止め、地方自治を守り発展させるために、すべての単組が、保育・子育て支援、学校の統廃合、高齢者の生活実態、地域経済、地域医療、行財政分析など、住民の暮らしと地域、自治体にかかわる課題の一つ以上を取り上げ、実態調査や関係諸団体との懇談を通じて提言運動に取り組むことをめざします。
(3)2010年10月に開催予定の「第8回東京地方自治研究集会」は、翌年4月に実施される見込みの都知事選挙に向けて、都民本位の都政政策を大きな共同の力で創り出すための集会として成功させます。同時に、2010年10月に岡山で開催される第10回地方自治研究全国集会にむけて、職場、地域で憲法をいかす運動を全面展開し、成功のために奮闘します。
(4)「財政健全化法」が公営企業会計などを含めた新たな指標で自治体財政を管理することなど地方財政制度の現状と問題点について明らかにし、地方財政制度の民主化へむけた取り組みを進めます。
(5)「東京都の予算分析パンフ」を東京自治問題研究所と協力し、発行します。
3)国政、都政、市区町村政の民主化をめざす闘い
(1)改憲、消費税増税、比例定数の削減など、自民・民主両党のマニフェストには国民にとって危険なものがあります。2010年7月には参議院選挙が行われます。組合員の政党支持・政治活動の自由を保障し、私たちの要求を実現させる立場から政治啓発活動を強めます。
(2)2011年4月に行われる都知事選については、都民本位の政策づくりを行うとともに、別途方針を決定し臨みます。自治体労働組合としての諸要求実現の立場から、民主都政確立のために奮闘します。
(3)多摩市長選(2010年3月)、品川区長選(2010年10月)など、区市町村の首長選挙については、当該単組の推薦決定等に基づき推薦決定を行い、民主自治体確立のために奮闘します。
(4)「革新都政をつくる会」や「都民要求実現全都連絡会」、「都民生活要求大行動実行委員会」に参加し運動を強めます。
Ⅴ.5万東京自治労連建設に向けた組織の拡大・強化
職場における組合活動が困難さを増すなかにあって、要求を実現する力となるのが「数の力」であり、組合の組織拡大・強化です。職場組合員に依拠した組合活動で、だれもが安心して働き続けられる職場づくりを進めることを追求します。
1.組織拡大の取り組み・・・自治体に働くすべての労働者を視野に入れた組織拡大を
1)新規加盟単組拡大にむけた取り組みを進めます。
2)新規採用・組合未加入者の組合加入の拡大について、春、秋の拡大月間を設定し取り組みの具体化をはかります。
3)自治体・外郭団体などに働く公務公共関係労働者の組合加入の働きかけを強めます。とりわけ、指定管理者制度が進み、新たな選定・公募により雇い止めが起きることが予想されます。雇用をまもる闘いと一体的に進めます。
4)臨時・非常勤をはじめ自治体に働く非正規労働者の組織化前進にむけ具体化をはかります。とりわけ、二重加盟役員会議を開催し組織化を加速的に進めるため意志統一をはかります。
5)自治体に働く委託・派遣労働者の組織化について、公契約運動と併せて運動を具体化します。
6)加入者拡大に向けたリーフの配布計画を策定します。
2.組織強化の取り組み・・・職場の隅々へ組合員の力を借りて(気軽に参加・・だれでも、いつでも、どこでも組合活動)
1)組合員の身近な要求をつかむためにも、職場懇談会を重視した組合活動を進めます。職場活動を活性化させ、組合員参加を広げ、新たな役員の担い手づくりを意識的に進めることを追求します。
2)労働協約締結権獲得を視野に、正規・非正規を含む「職場過半数労働組合組織」確立をめざし、要求活動と組織化を進めます。
3)職場要求書を確立し、36協定など職場段階での協約締結を進めます。
4)単組活動強化を図り、組織拡大を進めるうえでも次世代の役員育成と青年部確立は喫緊の課題となります。次代を担う青年部運動を強化します。
5)地域における未組織労働者の組織化、労働争議支援など単組が地域活動の軸となって地域組織強化の取り組みを進めます。
6)自治体業務の職の専門性を発揮し、政策提言・地域運動強化を図る観点から職域部会・協議会の運動を充実します。
7)多摩地域における自治労連運動を推進する三多摩協議会の活動を強化します。とりわけ、「自治労連と共同する会」、「三多摩現業懇談会」と連携した運動を進めます。
8)都本部機能強化と単組・補助組織・職域部会の運動強化のために、毎月1回の拡大中央執行委員会を開催し意志統一を図ります。
9)自治労連書記政策(案)の討議を深め、書記局機能強化にむけた取り組みを進めます。
10)第11回東京自治労連組織集会を開催し、自治体・公共関係職場をめぐる情勢の共有化と運動の課題・取組みを明らかにします。(7月頃)
11)公務公共関係労働者の組織化を加速的に進めるための方策について、引き続き議論を深めることとし、組織化の飛躍をめざします。
3.学習教育、宣伝、文化スポーツ活動
1)学習・教育活動を推進します。とりわけ、自治労連が主催する労働学校への参加や勤労者通信大学の受講を働きかけます。
2)結成20年を間近に控え、東京自治労連がこれまで果たしてきた役割、今後の運動のあり方など顧問団を講師として学習を行います。
3)労働学校の開催については、関東甲越ブロックとの共同開催も含めた検討を行います。青年層や新たな役員が参加する学習活動を強めす。
4)機関紙・FAXニュース定期発行します。さらに、組合員への情報提供としてのホームページの充実を図ります。
5)全国囲碁・将棋大会に向けて、囲碁・将棋大会(5月頃)を開催します。
6)自治労連全国スポーツ大会に向け、野球大会(4月)・女子バレーボール大会(7月頃)を実施します。
4.東京自治労連成20周年記念事業の取り組み(2011年3月)
「東京自治労連結成20周年記念誌発行」を行います。そのために「結成20年東京自治労連のあゆみ」作成委員会(仮称)を立ち上げます。
Ⅵ.自治労連共済を組織拡大と一体で進め、過去最高の到達点を実現する取り組み
1. 共済事業をめぐる情勢と自治労連共済東京支部の課題
1)昨年の世界的な金融危機は相次いで生保・損保業界の経営危機を誘発し、日本でも昨年10月には保険・損保業が経営破綻しました。郵政民営化にみられるように、外資系生保・損保業界と日本の保険業界による「自主共済潰しと市場化・開放」を求める動きは依然、日本経済への大きな圧力となっています。新保険業法の下で、自主共済事業は少額保険業への衣替えか、廃止を選択せざるを得ない事態を迎えており、労働組合の共済事業も今後2011年の保険業法見直しによる「適用除外見直し」攻撃も無視できません。来年2月に発足する全労連共済には自治労連共済も参加し、これまで積み上げてきた労働組合の助け合い事業の基盤を強化するとともに、未組織労働者を視野に入れた共済事業としてスタートします。
2)自治労連共済を組合員の身近な暮らしの相談役として位置づけ、組合活動を職場で拡大・強化していくために自治労連共済未加入者を対象とした取り組みが重要です。
全国多くの組合が実施した2009年度の新人組合員を対象とした「加入キャンペーン」や東京支部の「役員向け」、「組合員向け」説明会など、旺盛に取り組んだ経験を今年度の活動にいかします。
2. 具体的な取り組み
1)東京自治労連の「春・秋の組織強化・拡大」月間に併せた「加入者拡大キャンペーン」を展開します。
2)新入組合員・若手組合員の加入促進のため、「セット共済プレゼント」などの取組みの強化をはかります。
3)自治労連共済未加入者を30人に一人以上を加入させることを目標とした「単組訪問説明会」を開催します。
4)自治労連共済主催の「共済実務者研修会」(11月13日)や第17回共済学校(2010年2月4日~6日)に全担当役員・実務担当者の参加をめざします。
5)労働組合共済・自主共済事業への規制強化に対して、「共済の今日と未来を考える東京懇話会」に参加し労働組合共済・自主共済事業をまもるための集会や署名等の活動を取り組みます。
Ⅶ.各分野の闘い
1.青年分野
東京自治労連本部青年部方針の具体化を進め、本部・単組が一体となって、次代を担う役員育成をめざして運動を進めます。
1)青年部活動を活性化させ、次代を担う役員育成づくり
① 東京自治労連青年部活動の活性化のため諸行動への役職員の配置や講師派遣、財政援助を行います。
② すべての単組から青年部役員を選出できるよう単組と意志統一を図ります。
③ 青年層が積極的に諸行動へ参加できるよう青年部委員会へ働きかけを強めます。
④ すべての単組における青年部確立にむけ、本部青年部と単組執行部との懇談を進めます。
2)憲法と平和をまもる取り組みを重視した運動
① 青年組合員を対象とした、憲法・平和問題などの学習を積極的に進めます。
② 原水爆禁止世界大会、日本平和大会、3・1ビキニデー集会など平和の取り組みに青年層の参加を意識的に進めます。とりわけ、来年5月開催のNPT再検討会議にむけ、署名や宣伝行動、集会参加を強めます。
③ 「憲法をいかす自治体労働者東京連絡会」の運動に積極的に参加します。
3)学習活動を重視し、交流を深める取り組み
① 勤労者通信大学の受講を働きかけます。
② 自治労連が主催する労働学校等へ積極的に参加します。
③ 青年部が主体的に関わり、毎年実行委員会を立ち上げて継続的に行われている「東京の自治体に働く青年交流会」の成功にむけ取り組みを強めます。
④ 東京自治労連結成20周年にあたり、青年部として積極的な参加を検討します。
2.現業分野
総務省の指導・圧力による現業職場の民間委託・民営化を阻止する運動と現業労働者の賃金・労働条件改善の闘いを進めます。
1)東京自治労連現業評議会及び各単組現評の組織強化を図ります。
① 幹事会・常任幹事会を定期開催し意志統一を図ります。
② 現業職場の民間委託・民営化問題を学習し、違法な職場実態を根絶させるため奮闘します。
③ 民間委託・民営化された職場の労働者との懇談を進め、賃金・労働条件改善を進め、組織化へつなげます。
④ 民間委託が進む給食・用務などの職場において、法令を遵守させ、新たな民間委託阻止・新規職員採用にむけた取り組みを進めます。
2)各種の集会成功にむけて奮闘します。
① 「10・15自治労連現業全国統一行動・東京自治労連総決起集会」の成功にむけて奮闘します。
② 現業組合員が諸行動へ積極的に参加し、要求実現にむけた取り組みを強めます。
③ 現評が独自に主催する「現業春闘討論集会」を開催します。
3. 女性分野
人間らしく働くルールの確立、男女平等参画社会の実現、女性の地位向上、母性保護拡充・差別撤廃など女性が働く上での諸要求実現にむけて運動を進めます。
1)憲法闘争を運動の軸に、駅頭宣伝(ブロック別)や、署名活動を旺盛に進めます。
2)昇任・昇格差別をなくし、セクハラ・パワハラ防止にむけアンケートを活用した運動を進めます。
3)女性部が毎年実施する「女性部春闘決起集会」を開催し、春闘期の運動を強めます。
4)歴史と伝統がある母親大会(日本・東京)働く女性の中央集会、自治体に働く女性の全国交流集会など各種の集会を成功させる立場で奮闘します。
5)福祉関連要求実現のために対都・区・市に対する要請を行います。
4.公務公共関係分野
自治体業務の市場化が進むもとで、非正規・公務公共関係分野の運動はますます重要となります。公務公共一般、介護労、都庁法人、東文労、公務公共関係単組の運動を交流し、組織拡大・強化を運動の軸にしながら、不当な雇い止め、賃金引き上げの運動を進めます。
1)未組織公務公共関係労働者の組織化を飛躍的に前進させるため、関係単組の意志統一を深めます。
2)最賃引き上げの闘いや人事院「非常勤指針」、「改正パート労働法」を活用した運動を進めます。とりわけ、自治労連本部が作成した「臨時・非常勤職員検討委員会報告書」について均等待遇実現の立場で学習を深めます。
3)指定管理者制度における「公募の再選定」などにより、労働者の雇用が奪われることが予想されます。雇用をまもる闘いを組織拡大と一体に進めます。
4)自治体のあらゆる職場の広がっている「有期雇用制度」により、雇用更新を繰り返し、年度末に雇用不安をかかえる労働者が増大するなかで、雇用年限撤廃の闘いを進めます。
5)本格的・恒常的に自治体業務を担っている非正規・公務公共関係労働者が主体的に自治体労働者論などの学習を深めます。
6)正規・非正規労働者が一体となった組織化を進めます。